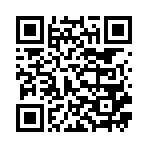2012年09月30日
グリップセフティをカスタム
今夜は関東地方を台風が通過するのかな?
J-Armory MEUベースでオリジナルカスタムガバ(オラガバ?)を作っている訳なんですが、もともとのパーツをそのまま仕上げ直すんじゃ面白くない。
なので、ちょこっと変化を付けたい。
一昨年のクリスマスぐらいだったか、WAがジャンクパーツを寄せ集めたクズ袋、もといパーツ袋というのを店頭販売だけじゃなくネット通販でも始めて、自分も1万円ぐらいのやつを購入しました。
その大半は使い道がなく、そのままジャンクボックスに仕分けされたまんまになってます。
正直無駄遣いだったなと思います・・・。
今回はそのパーツ袋の中からグリップセフティを。
右の真ん中のやつです。
これはSV系についてるやつでしょうか?
かなり肉厚なのと、変な波型のセレーションが入っていて好みじゃなかったので、いつか機会があったら加工して何かに付けようと思ってました。
もちろん、波型セレーションは削り落として。
波型セレーションを何とか除去したら、次は胴回りやテイル部分をマーカーでアタリをつけたラインに形状を合わせていきます。
左がもともと付いてたグリップセフティ。
うちのタクティカル系はみんなコレがついてます。
ハイグリップした時に解除されないことが多いんですが、きっと自分の手に合わないんでしょうね。
ラインを合わせてみました。
似てるようで大分形状が違います。
決定的に違うのはハンマー受けの窪みの部分。
フレームからグリップセフティへと流れるようなラインを出せたらとても格好良くなります。
しかし自分は先にフレームの仕上げ直しを済ませちゃったんで、今からライン合わせはもう無理ですw
先にこっちをやってからだったら良かったな。
2012年09月28日
プロフェッショナル・カスタム
M1911 U.S.ARMYの仕上げ直しは完成しましたが、並行して仕上げ直し中のJ-Armory MEUの塗装も終わっています。

下地にシルバーを塗って、上塗りにエコブラ(ブラックパーカー+パーカーシール混合)ですが、下地作りに時間をかけたので、カッチリとしてとても綺麗に出来ました。
まるでメタル削りだしの上下に見えるほど!
(純正HWですよ♪)

今回はきっちり平面出しをしたし、鋸歯のセレーションもカッターナイフで削いでエッジを利かせたので納品直後の新品状態みたい!

太く彫り直した刻印もバッチリ。

もともと中古品で破格の¥8,300-でゲットしたブツだから、こんな風にリアルダメージがそこかしこにあったもんですが・・・

すっかり綺麗になりました。
綺麗すぎて、このままビンテージ処理しないでもいいかなって気がしてしまう。

カッターで削いでエッジを立てたセレーション。

スライド内側の要らない溝もプラリペアで埋めました。
溝の縁を奥に向かって広がるようにカッターで削ってからプラリペアを入れたので、剥がれて取れる心配はありません。

そして実銃通りの形状で、エジェクションポート内側の拡張もつけました。

この頃かならずやっている、スライド下の三角の穴も埋めて処理しました。

今回はMEUではなく、プロフェッショナルベースのオリジナルカスタムという感じで行くつもりです。
現在は金属パーツの黒染めをやってますが、ハンマー、グリップセフティ、MSハウジングはもともとのMEUと変えるつもりです。
下地にシルバーを塗って、上塗りにエコブラ(ブラックパーカー+パーカーシール混合)ですが、下地作りに時間をかけたので、カッチリとしてとても綺麗に出来ました。
まるでメタル削りだしの上下に見えるほど!
(純正HWですよ♪)
今回はきっちり平面出しをしたし、鋸歯のセレーションもカッターナイフで削いでエッジを利かせたので納品直後の新品状態みたい!
太く彫り直した刻印もバッチリ。
もともと中古品で破格の¥8,300-でゲットしたブツだから、こんな風にリアルダメージがそこかしこにあったもんですが・・・
すっかり綺麗になりました。
綺麗すぎて、このままビンテージ処理しないでもいいかなって気がしてしまう。
カッターで削いでエッジを立てたセレーション。
スライド内側の要らない溝もプラリペアで埋めました。
溝の縁を奥に向かって広がるようにカッターで削ってからプラリペアを入れたので、剥がれて取れる心配はありません。
そして実銃通りの形状で、エジェクションポート内側の拡張もつけました。
この頃かならずやっている、スライド下の三角の穴も埋めて処理しました。
今回はMEUではなく、プロフェッショナルベースのオリジナルカスタムという感じで行くつもりです。
現在は金属パーツの黒染めをやってますが、ハンマー、グリップセフティ、MSハウジングはもともとのMEUと変えるつもりです。
2012年09月24日
ミリガバ3兄弟

前回は夜の撮影だったので、さっき朝の室内光で撮影したミリガバ3兄弟です。
まあフラッシュ焚いての撮影ですけどね。
三色揃うとなかなか感無量ですw
前回の撮影時に、実は完成と言いながら一つ欠けていたものが。
それがマガジンでした。
もともとSCWバージョン1のM1911 U.S.ARMYに付属のマガジンはこれ、旧タイプのシングルカラムです。
しかもベタッと例のロイヤル青塗装がされてて、本体を綺麗に仕上げ直してもマガジンがコレじゃあ・・・って感じ。
なので現行のシルバーマガジンを一つ頂戴することにしました。
カンペのリムーバーで塗装を剥離。
非常に反応が良いので楽でしたよ♪
べろり〜ん。
塗装の下から亜鉛地肌が現れました。
あまり白化しておらず、綺麗な銀色。
塗装で保護されていたんですね〜。
塗装を剥離するのに、完全に分解してしまいたかったんですけど。
なんだ、このバルブ、WAの独自仕様??
持ってるバルブレンチは使えないではないか!
つか今まで全然気づかなかった。
普段金属のカラーで隠れてますからね〜。
というわけで完全分解は断念し、余計なところはマスキングしてカンペリムーバーを塗りたくりました。
むき出しになったマガジンを一応シャイネックスのスポンジヤスリで磨きまして・・・。
バーチウッドのスーパーブルーでブルーイングでっす♪
綿棒でチマチマ塗るのが自分流。
うほっw
無光沢なミリタリーテイストマガジンになったよ。
この状態まで染まったら、使い倒してヘロヘロになったシャイネックスで表面を磨きます。
ススが落ちて綺麗な光沢が出ました。
うお〜塗装とはぜんぜん違う、金属地肌バリバリ〜。
まだ仮組みだけど、ARMYたん専用マガジン完成♪
2012年09月19日
ビンテージブルー塗装
ガスブロMP5やMP9に浮気しつつもしっかりガバの仕上げ直しは同時進行中。
実際3丁のガバが塗装を終えて乾燥待ちの状態なので、1丁目を組み上げて完成させることにしました。

WA M1911 U.S.ARMYね。
初めてのブルー塗装で、初めてのブルースチール使用で思った以上の出来栄えにウットリ。
実銃の写真を何枚も集めて参考にして、実際には見たこともないものを想像しながら仕上げました。
かつてのロイヤル青塗装の面影はもう無い。

パーカーベースでビンテージ塗装したM1911A1、エコブラで現用ダメージ塗装をしたMEU、そして今回はブルービンテージのM1911。
うちのミリガバ三兄弟が揃いました♪
もうこれでミリガバに思い残すことはありません。




あ〜三脚の脚が入っちゃった、サイアク〜〜ww

今回うまくいったな〜と思えるのは、本体のブルー塗装と実際にブルーイングした金属パーツとの間に違和感がほとんど無く出来たこと。
本体塗装前に金属パーツの染を先にやったおかげで、色を出来るだけ合わせることが出来たと思う。
ブルースチール単色だともっと不自然な感じだったでしょう。
クリヤーイエローをたっぷり混ぜたおかげで凄くリアルになりました。


掟破りの手持ち撮影w
角度が変わると色味も変わるブルーイングの質感が、塗装でありながら良い感じに出てます。

エジェクションポート内側の溝はプラリペアで埋めて無くなった。

SCWバージョン1からバージョン3へ機構変更し、トランスファーハンマー仕様でファイアリングピンの突出はもうありません。
熱湯矯正でスライドのガタはすっかりなくなり、逆にきついぐらいタイト。
なんだろう、チャンバーカバーのあたりを見るとスライドトップが異様に肉厚がある。
WAサイズってこんなだったっけ??

エジェクションポートの内側を覗いたあと、きちんと閉じきってなかったかな?
まだ組んだばかりで作動は渋いです。
でもガチャガチャ動かす気にはとてもなれない。
本体は全体にヘアラインを入れるようにして磨いてあります。

スライド下部の三角形の穴も埋めてあります。

1丁10万超のエランガバなど買えはしない。
てか見たことすら無いw
でも¥8,980-で入手した中古のWAガバでそのぐらいのものを目指したかった。

だからせめてグリップぐらいは奮発したさw
このグリップにダメージ処理を加える勇気はないんだよね〜。

リアサイトからハンマー、グリップセフティ、MSハウジングへと続くメタルパーツと塗装した本体部分に違和感はない。
チェッカーもグルーブも刻まれてないツルツルのハウジングがやたらセクスィ~♪



ゴリゴリ削って薄くしたダストカバーは手に持った時のスッキリ感が違います。
でも言われなきゃ気づかない程度。
バレルブッシングも勿論ブルーイング。

二段階に表面を削って薄くしたサムセフティがお気に入りです。


刻印は大変だったけど綺麗にできた。


デザインナイフで削ぎ削ぎしたコッキングセレーションも、おかげでエッジがキリッと切り立って触り心地がいいです。

我が家の超高級路線のナショナルマッチ銀とツーショット。
また眺めるだけで撃ちたくないガバが一つ増えたか・・・・。
実際3丁のガバが塗装を終えて乾燥待ちの状態なので、1丁目を組み上げて完成させることにしました。
WA M1911 U.S.ARMYね。
初めてのブルー塗装で、初めてのブルースチール使用で思った以上の出来栄えにウットリ。
実銃の写真を何枚も集めて参考にして、実際には見たこともないものを想像しながら仕上げました。
かつてのロイヤル青塗装の面影はもう無い。
パーカーベースでビンテージ塗装したM1911A1、エコブラで現用ダメージ塗装をしたMEU、そして今回はブルービンテージのM1911。
うちのミリガバ三兄弟が揃いました♪
もうこれでミリガバに思い残すことはありません。
あ〜三脚の脚が入っちゃった、サイアク〜〜ww
今回うまくいったな〜と思えるのは、本体のブルー塗装と実際にブルーイングした金属パーツとの間に違和感がほとんど無く出来たこと。
本体塗装前に金属パーツの染を先にやったおかげで、色を出来るだけ合わせることが出来たと思う。
ブルースチール単色だともっと不自然な感じだったでしょう。
クリヤーイエローをたっぷり混ぜたおかげで凄くリアルになりました。
掟破りの手持ち撮影w
角度が変わると色味も変わるブルーイングの質感が、塗装でありながら良い感じに出てます。
エジェクションポート内側の溝はプラリペアで埋めて無くなった。
SCWバージョン1からバージョン3へ機構変更し、トランスファーハンマー仕様でファイアリングピンの突出はもうありません。
熱湯矯正でスライドのガタはすっかりなくなり、逆にきついぐらいタイト。
なんだろう、チャンバーカバーのあたりを見るとスライドトップが異様に肉厚がある。
WAサイズってこんなだったっけ??
エジェクションポートの内側を覗いたあと、きちんと閉じきってなかったかな?
まだ組んだばかりで作動は渋いです。
でもガチャガチャ動かす気にはとてもなれない。
本体は全体にヘアラインを入れるようにして磨いてあります。
スライド下部の三角形の穴も埋めてあります。
1丁10万超のエランガバなど買えはしない。
てか見たことすら無いw
でも¥8,980-で入手した中古のWAガバでそのぐらいのものを目指したかった。
だからせめてグリップぐらいは奮発したさw
このグリップにダメージ処理を加える勇気はないんだよね〜。
リアサイトからハンマー、グリップセフティ、MSハウジングへと続くメタルパーツと塗装した本体部分に違和感はない。
チェッカーもグルーブも刻まれてないツルツルのハウジングがやたらセクスィ~♪
ゴリゴリ削って薄くしたダストカバーは手に持った時のスッキリ感が違います。
でも言われなきゃ気づかない程度。
バレルブッシングも勿論ブルーイング。
二段階に表面を削って薄くしたサムセフティがお気に入りです。
刻印は大変だったけど綺麗にできた。
デザインナイフで削ぎ削ぎしたコッキングセレーションも、おかげでエッジがキリッと切り立って触り心地がいいです。
我が家の超高級路線のナショナルマッチ銀とツーショット。
また眺めるだけで撃ちたくないガバが一つ増えたか・・・・。
2012年09月16日
MP9システム7 その4
KSC MP9の逆輸入バージョンとして国内で販売されていた海外仕様のシステム7版です。
サイトの商品写真では不鮮明ながら、KWAがアメリカなどで販売してる「KMP9」の刻印がされたバージョンでしたが、実際届いてみたら香港などで売られているリアル刻印のものだったのでバンザイ歓喜しました。
日本版は素材がファイバー樹脂であるためか、レーザー刻印が不鮮明で残念だったポイントの一つでしたが、海外バージョンはカッチリとスタンプ刻印がされてますね。
ボルトの刻印もCal 9x19mmとなってます。
北米版はcal 6.00 mmとエアソフトガンであることを示す刻印になっていましたので、そっちだったら塗り潰そうかと思ってました。
シリアルナンバー刻印は日本版では固定ですが、海外版は個体毎か、ロット毎かは知りませんがそれぞれナンバーが違うようです。
前回までシステム7の海外版と日本版の内部構造の違いを見てきましたが、もう少し取り上げられる部分もあったので追加します。
上の写真はシステム7版のアウターバレル。
海外のサイトではアウターバレルがスチール製だとアチコチで書かれていたのでワクワクしてたんですが、実際はプラ製でした。
彼らの言うアウターバレルとはいわゆるハイダー部分、バレルガードのことだったみたいです。
しかし日本版と比べると同じプラ製とはいえ質感がとてもいいです。
ちなみに日本版がこっち。
プラスチックがテカテカしてて安っぽく見えます。
実際は外部に露出することはないのでそれほど気になりはしませんが。
アウターバレルといえば、チャンバー部の下にある突起ですが、以前自分はこの部分を折ってしまってKSCから替えのパーツを取り寄せたことがあります。
金属パーツのフィーディングランプと接続する部位としては華奢なので、取り扱いに慎重さが必要です。
システム7版はこの根元部分が少し強度アップしてました。
日本版では切れ込みが入っていた根元の部分が、厚みを多く設けてあります。
マズル部分から見たインナーバレルです。
上の日本版はアウターバレルの先端までインナーバレルが突き出ていました。
システム7版はアウターバレルの凹んだところまでインナーバレルが後退しています。
それにしてもブラストをかけたようなアウターの質感はとてもいいですね。
ボルトキャリアも並べると違いがあることがわかります。
両者とも素材はアルミダイキャスト製のようなんですが、外側をあとから切削加工してるようです。
で、日本版は表面を黒染してますが、システム7版は塗装です。
この辺の質感は日本版に軍配を上げたいと思います。
また日本版は矢印の部分がシステム7版と比べて肉厚になっており、その分重量も多いようです。
システム7版のガイドロックのところに紐が結ってあるのは、自分が分解しようとした時スプリングが飛んで顔にあたったもので、もしこれが目にあたってたら大変なことになるところでした。
なので今後のために紐でスプリングとガイドロックを結わえておいたものです。
遊び心でトップカバーを取り替えてみました。
日本版ロアフレームにシステム7版のアッパーフレームは取り付けることができましたが、逆はダメでした。
裏返してみると日本版アッパーフレームの方は矢印部分に突起があり、これがシステム7のロアフレームだと干渉してしまいます。
またこうして見比べると両者とも別々の金型で作られてるのがよくわかります。
互換性ということで言えば、両者の間で全く同じパーツは殆ど使われておらず、かなり低いようです。
さて前回の最後に、「海外の先輩たちが、購入したらまず最初にコレやっとけと言う、システム7版MP9のTipsを紹介します」と約束したので、実際行ったものを紹介します。
上の写真はシステム7版のエンジン部。
髪の毛よりも細いノズルリターンスプリングが小さな突起に引っ掛けてあるのが判ります。
海外のユーザのサイトでは、この突起からスプリングが外れてシリンダーのカップに挟まってグチャグチャになるという報告が多いようです。
なので、購入したらまずその対策をやっとけという有り難いTipsをいただきました。
まあ自分が行ったのは単純にゼリータイプの瞬着を盛りつけて固定するってだけなんですが。
アルコールで脱脂したあと爪楊枝の先で瞬着を取って塗りつけました。
前と後ろ、これで万全です。 たぶん・・・
もう一つはボルトキャリアの側面下部。
ここが使用してると激しく削れるらしいんです。
自分のもすでに塗装が禿げてるんですが、海外のユーザが言うには削れたアルミ片が内部に溜まるほどだそうな。
その原因がフィーディングランプのボルトストッパーの突起で、このスチールパーツのエッジが尖ってるために、擦れる側のボルトキャリアが削れるということです。
なので購入したらまず、このエッジを研磨して丸めておけとのこと。
写真はすでに削った後です。
他にもオートマチックシアーのスプリングが強すぎるから、ペンチで伸ばせみたいなこともありましたが、それはパスしましたw
2012年09月15日
MP9システム7 その3
MP9の日本版と、海外仕様のシステム7版、その違いを比較検証するシリーズの3です。
前回メカ部を紹介しました。
今回は給弾、発射のエンジン部分をチェックしたいと思います。
ここには私が熱望した最大の感涙改良ポイントが有ります!
それは・・・?
まず、日本版MP9を購入して私が常に苦しめられて来た事。
まずはBB弾がチャンバー内にうまく収まらずボルトが閉鎖不良を起こすジャム、それに伴うノズルの変形。
そしてチャンバー内に収まったものの弾の位置が前進し過ぎて、フローティングバルブが閉じてしまい、発射側にガスが回らずブローバックだけしてしまい、次弾をチャンバーに給弾してしまう二重装填。
こんな事が購入直後から頻発しました。
私が持ってるGBBガンで他にこんなめんどくさい奴はありません。
WA M4も出始めの頃は散々言われたものです。
しかしあちらはその後、豊富なカスタムパーツが発売される事によって所有者の力量次第でどうにでもなりました。
KSC MP9は・・・私の知る限りでは不等ピッチのリコイルスプリングぐらいでしょうか?
MP9もちょっと改良すれば俄然安定したGBBガンに生まれ変われるだろうに・・・。
そんな思いが有ったのです。
まあ私の力量ではカスタムパーツ頼みなので、無いものをゼロから作る事は出来ませんw
自分が心から望んでた事の一つがコレ。
マガジンリップのBB弾保持形式。
過去記事でも何度か愚痴を垂れてますが、ダブルカラムのままリップで保持される日本版マガジンでは、ノズルのインパクト部分が中心ではなく左右両端に偏る為に角が潰れ易く、それによって益々ファールチップしてジャムを起こし易くなります。
これが改良されたのは正に感涙もの。
エジェクションポートから覗いた図です。
見やすいように色付けしていますが、右の白いのが初弾で、赤く色を付けたのが次弾です。
このように日本版ではリップからBB弾を打ち出すのが非常に窮屈に感じられると思います。
また、弾がチャンバー内に収まるまでに段差がかなりあって、これが弾噛みの原因になりそうな感じが見て取れますよね。
その部分を取り出すとこのようになっています。
バレルアッセンブリとフィーディングランプです。
マガジンのリップから打ち出された弾は、フィーディングランプの三日月型の面取り部分を乗り越えて、バレルの厚み、ラバーチャンバーの厚みといった段差を越えてチャンバー内部の定位置に収まらなければならない訳です。
角度を換えて見てみます。
三日月型の部分にカーンと当たって跳ね上がった弾が、上手にチャンバーの中に入り込むのが理想でしょうが、実際はあり得ないところに飛んで行く困ったちゃんもいるのです。
さて、今度はシステム7の方です。
初弾は中心に見えており、次弾はまだ下にあって隠れています。
弾は中心にありますから、ノズルのインパクト部もまっすぐド真ん中をヒットします。
そして弾の前方に何かがあるのが解りますよね?
ハイ!
この通りです♪
解りますか皆さん!
これですよ!!
ここまで改良されていたんです!
余計な説明はいらない、見たまんまです!!
嬉しさのあまりジャパネットの社長さんみたいに叫んでしまいますw
さあ、ここまでで給弾経路の問題がかなり改善されてる事が解りました。
これでジャムの発生率はかなりゼロに近くなったのではないかと思います。
私が自分で出来るものならしたかったことが、ここまで実現しています。
そしてまだ、更に次があるんです!
日本版のローディングノズル、ピストンとシリンダーの関係からいえばシリンダーになります。
マルイのグロックなんかもこんな感じで、ノズルがピストンになってるWAとは対照的ですね。
で、ガスルート開口部から覗くフローティングバルブの状態は、バルブの後ろにスプリングが有り、発射方向のルートを強制的に閉じるようになってます。
すなわちチャンバー内の定位置に収まったBB弾がフローティングバルブを押しこむ事によって、発射方向の弁が開き、BB弾が発射される訳です。
BB弾が定位置を行き過ぎてチャンバー内に保持された場合、ガスは発射側へ行かず、それが弾ポロ・二重装填の原因になります。
これはWA M4で頻発するマグナの持病と同じ原理です。
そしてその有効な解決法はご存知、負圧化ですね。
(MP9は厳密にはもともとミドルシュートの負圧式)
システム7のエンジン部を取り出してみてみましょう。
シリンダーリターンスプリングが有ります。
ピストンと分離。
シリンダーの内部を後ろから見た図。
前方にフローティングバルブが有り、抜け留めとしてピンが刺さっています。
シリンダーのカップの薄さが気になりますね。
海外ではこのカップ部分が割れるトラブルが非常に多いようです。
私はここが現状気がかりを残してる部分だと思います。
おっと、話が脱線しました。
ノズル部を前から見ると、フローティングバルブは三枚羽の金属製だというのが判ります。
そしてスプリングはバルブの前方、すなわち常に発射側へのガスルートを開けておき、BB弾が発射されたあとの負圧によって弁が閉じるようになっています。
これでBB弾が定位置を行き過ぎてチャンバー内に保持されたとしても、弾ポロの発生は限りなくゼロに近づいたと思います。
MP9がよく言われる、弾を選ぶ機種ということが、これによって弾を選ばない(一般的な規格内で)奴に変わったと言えるんじゃないでしょうか。
いかがでしたでしょうか?
私が悩まされて来たMP9の持病とも言えるジャム、弾ポロ・二重装填、ノズルの変形・・・。
それらがなんと、マガジンリップ、フィーディングランプ、負圧ノズルと3重の改良によって見事に消化されたと言えると思います。
これを感涙にむせばずしていかがしましょうや。
そして購入から現在までの間、システム7版で一度もトラブルは起きていません。
日本版(エクセレント・ハードキック版)とは違うのだよ〜フハハハハ。
ウルァッ! (((((;`Д´)≡⊃)`Д)、;'.・ゲフゥ!
・・・・そんな訳でして、長々とお付き合いしてくださってどうもすいませんでしたm(_ _)m
大体こんなところで大まかな改良点はおしまいです。
次回は・・・海外の先輩たちが、購入したらまず最初にコレやっとけと言う、システム7版MP9のTipsを紹介します。
2012年09月14日
MP9システム7 その2
MP9の日本版と、海外仕様のシステム7版、その違いを比較検証するシリーズの2です。
二つを撃ち比べてみると、そのブローバックリコイルの迫力がまるで違うという事をここで今一度確認しておきたいと思います。
マンガ風に擬音で表現するならば、日本版は「タンッ! タンッ!」という感じ。
システム7版は「バキンッ! バキンッ!」という感じ。
手首に来る衝撃がシステム7の方が鋭く、リコイルスプリングが金属音を響かせます。
また海外のユーザが話題にもしていますが、撃つ度にチャージングハンドルの下の隙間から顔に向かってガスが吹き付けてきて、それが目に当たります。
ボルトが後退する勢いで空気(またはブローバックガス)が後方に押し出されるのではないかと思います。
まあとにかく大迫力!
さて、前回はパッと見、外観の違いを見て来ましたが、今回はいよいよ内部へと切り込んで行きます。
過去記事でも日本版MP9の矢印の部分の強度不安に触れた事が有ります。
ブローバックするボルトの衝撃を受け止めるのは1本のリコイルスプリングガイドなんですが、それを支えているのがロアフレームのプラスチック部分である事。
それがやはり不安と見えて、分厚いスポンジのクッションを二枚重ねでインナーシャーシ後端に両面テープで貼付けると言う「にわか対策」がされています。
このクッションバッファーが無ければ、ボルトはインナーシャーシに当たる程後退しませんから、スプリングガイドロッドがガツンと押しとどめる訳です。
するとやはりTMP時代にはフレーム後部が割れて吹っ飛んだことが有ったようです。
システム7はこの通り、見たままに改良強化されているのが判りますね。
スプリングガイドロッドの基部がインナーシャーシの延長された鉄板で補強されてます。
「にわか対策」と表現したスポンジ2枚重ねのバッファーが、システム7ではリコイルバッファーとして、分厚い金属のベースとゴムの板を合わせたパーツがインナーシャーシにビスで固定されました。
日本版のリコイルスプリングガイドロッドですが、先端に穴が開いていて、過去の記事でも触れましたがゴムのチップが入ります。
以前千切れていたので交換したのですが、今回あれからさほど撃ってもいないのですが、見たらやはりまた千切れてたので捨ててしまいました。
システム7の方はといえば、もうすっかり穴すら無くなっていました。
あの先っぽのゴムはやっぱいらないんだと思いますw
つづいてメカ部分を見てみましょう。
今度は先にシステム7の方から。
写真はハンマーがリリースされてデコックされた状態なんですが、ハンマーがボルトの後退によって後ろに倒れると爪がシアーにかかってコッキングされた状態に成ります。
シアーはトリガーバーと連動しており、トリガーを引くとシアーが後ろに引っ込んでハンマーをリリースします。
ものすごくシンプルです。
そして発射後ボルトが後退するときトリガーバーとシアのリンクが一旦断たれて、シアーだけがまた前に出てハンマーを引っ掛けます。
フルオートにすると今度はトリガーバーとシアのリンクが断たれなくなり、トリガーを引いてる間はシアーは引っ込んだままになって、代わりにハンマーをフルオートシアが横から引っ掛けます。
フルオートシアはボルトが前進しきると前方に引っ張られ、ハンマーをリリースします。
さて日本版はと言えば・・・。
パッと写真では説明しようがない程複雑で、システム7のシアーと違って、トリガーを引くと後ろのメカがカニバサミのような動きをしてハンマーをリリースします。
なんとも静止画では説明しようがないんですが、この複雑なメカこそ実はMP9のリアルなメカを忠実に再現した物なのだそうです。
シンプルなシステム7と比べて複雑なこのメカは、何とも言えないネバいトリガーフィーリングを生みます。
引いたトリガーが引きっぱなしのまま戻らなくなったり、あまりいい印象は有りません。
リアルなメカなら日本版、確実な作動ならシステム7ということでしょうか。
フルオートは大体仕組みは同じかと思います。
システム7ではフルオートシアをスプリングで後ろに引っ張っていますが、日本版はフルオートコネクターの下にダンパースプリングというのが入っているようです。
すいません、この辺りはテキトーで・・・。
という訳で、またしても内部に弱点を補う感涙の改良がありましたね?
今回はメカ周辺をチェックしましたが、次回は給弾、発射のエンジン部分をチェックしたいと思います。
ここには私が熱望した最大の感涙改良ポイントが有ります!
メーカーへのアンケートハガキでお願いしたことが実現??
乞うご期待w
2012年09月12日
MP9システム7 その1
KSCが海外向けに作ったMP9で、日本では未発売のシステム7版・・・という事で良いのかな?
ちなみに海外ではKWAという台湾メーカーがKMP9という名前で様々なバリエーションを展開しており、本製品の仕様はそれと同じです。
ていうか、まんまKWAがKSCの委託で作ったもののような感じです。
今回はこのシステム7版を日本版と比較しながら、その違いを検証して行きたいと思います。
はじめに外観から、そして内部へと・・・。
2丁のMP9。
色が違うというのはさておき、まず素材感が異なります。
KSCのサイトによれば日本版は「新ファイバー強化ナイロン」採用の外装ですが、システム7版の方は普通のABSという感じです。
日本版はファイバー樹脂の独特な成型ムラが目立ち、あちこちにヒケやバリもあります。
正直これが実銃と比べてリアルなのかは分かりませんが、システム7版の方は逆にビックリするぐらい綺麗。
見たままに評価しますが、日本版はトップレールのところはパーティングラインがクッキリ残ってますし、バリが目立つところにボコッと有ります。
そう言えば購入直後にパーティングラインが指に食い込んで痛くて、トリガーガードの下からグリップ前部にかけてカッターの刃でこそぎ落とした記憶が有ります。
システム7の方はトップレールにパーティングラインは有りません。
ですがグリップやトリガーガードといったところはやはり同じように有ります。
チャージングハンドルの質感が両者で異なります。
チャージングハンドルはMP9ユーザなら誰でもご存知、プラスチックでパカパカとフレームとの隙間があいてて非常に安っぽく感じる部分です。
そういう物なのかなと、まあ納得するしか無い訳ですが・・・
ところがシステム7はこんなところもカッチリと改良されてて、ガタつきも無く、安っぽさは感じなくなりました。
パーティングラインも素材のテカリも無いですね。
刻印もこころなしかクッキリとしています。
ガバッと口を開いたグリップのマガジン挿入口。
トリガーガードのところに、ここにも大きなバリが有ります。
システム7は後ろに仕切りが有ります。
これはマガジンの挿入し易さやガタつき防止、フレーム自体の耐久性向上に寄与する改良かと思われます。
写真では切れてますが、トリガーガード下のバリは有りません。
折りたたみ式のストック基部です。
ここもMP9ユーザは皆、そのガタつきが気になってるはずの部分ですね。
私も過去の記事で、ここに瞬着を盛ってガタ取りをしています。
システム7は何と、この基部が別パーツで、しかも金属になってました!
さらにガタも無くなり、金属になった事で非常に剛性の点から安心感が向上してます。
さあ〜そしていよいよシステム7の核心部分に入って行く訳ですが〜。
マガジンはどちらもダブルカラムにてロングマグなら50発前後。
リップの形状が異なっており、システム7の方はリップの方に上がって来た弾は真ん中に寄せられ、ローディングノズルでチャンバーに送られるときは弾の中心線をとらえて打ち出されるため、非常にジャムリにくく改良されています。
また2列から1列に寄せられる分、装弾数はシステム7の方が少ないようです。
どっちにしてもお座敷派の自分はマガジンにフルに弾を込める事は有りません。
さらにフォロアーの開口部が日本版は射手の左側に有りましたが、システム7は正面側に変わってます。
日本版は専用のローダーで一気に弾込めが出来て気持ちがよかったのですが、システム7版は専用ローダーが無くなり、フォロアーを指で下げてリップから一発一発こめるしか有りません。
自分はマルイ製のBBローダーを使ってます。
マガジンを後ろから見たところです。
システム7は放出バルブを直に叩いてガスを発射するようになりました。
日本版の方はバルブの後ろにプレートがあり、てこの原理でプレートがバルブを押しこむようになってました。
プレートの奥にバルブが見えます。
そんな訳で外側からパッと見える部分の違い、改良点は大体こんな感じです。
次回はいよいよ内部へと・・・。
そこにはまた感涙の改良点が・・・。
2012年09月11日
MP9再生産と聞いて
自分が好きな銃の一つにMP9があります。
KSCがMP7をリニューアルして発売、続いてMP9も再生産と聞いて、久しぶりにMP9を我が家の武器保管庫から持ち出して撃ってみました。

そしたら相変わらず不発、弾ポロと絶不調w
これさえ無ければ最高なんですけどね。
ところで再生産を今回購入した人も同様に悩ましい体験をしてるのかと思い、Google検索してみたところあるものを発見しました!
アマゾンでKSC MP9逆輸入バージョンなるものが売っているじゃないですか。
しかも販売元はあの四つ星のお店。
もしやこれってMP9の台湾バージョンつって、システム7とやらになってる奴では??
自分は海外通販でパーツを購入した事は有りますが、銃本体は規制適合性で通関出来るかどうかという問題が有るのを聞いていて、やったことがありません。
でも普通に日本でも買えたんですね(しかもアマゾンで)。
VFCのMP5を買ってお金を一杯使ったばかりだから正直悩みました。
でも手元のMP9を撃てば弾ポロリンで我慢ならず・・・。

買ってしまいましたw
ダークアースバージョン♪
上の奴を塗り替えた訳じゃないですよw
ちゃんと買ったんだから!
しかも再生産の国内バージョンより安いじゃないの!

商品説明には逆輸入バージョンとは書いてあったけど、台湾KWAの箱に入って届くのかと思えばちゃんとKSCの箱に入ってました!
(ダットサイトやHOGUEのグリップスリーブはもちろん自分が後から付けたものです)

しかも日本語のマニュアルが!
でもどうせ既に持ってる国内バージョンと同じものでしょ?
と、思ったら・・・。

あれ?

ちゃんとシステム7仕様に改訂されているじゃん??

ちょ〜っw
パーツリストまで〜。
つかこのパーツ注文してKSCから送ってもらえるんだろうか??
んん?
何か気になる記載が・・・

なんと2010年に既にこのマニュアルは出来ていたと?
日本で販売する予定があったと言う事でしょうか?
なのに何でこの前、旧バージョンを再生産して、システム7は出さないのでしょうか?
判りません・・・。

とにかく2挺めのMP9に目尻が下がりっぱなしの私。
MP5もどこへやらw
肝心の実射性能は?
・・・はっきりいって別物です!
衝撃的に、なんか今までのMP9のリコイルがお子様向けと思えて来るほどガツンガツンきてぶっ壊れるんじゃないかと心配になるほどです!
そして、これまで不満だった給弾系が全て理想的な改良を受けて、これほど痒いところに手が届いた気持ちよさはかつて無いって程にバージョンアップしてました。
過去記事で散々愚痴って来たポイントがもれなく全て改善されていて殆どパーフェクトや〜!!
次回はその点を細かく比較検証して行きます〜。
写真撮りまくりましたので。
KSCがMP7をリニューアルして発売、続いてMP9も再生産と聞いて、久しぶりにMP9を我が家の武器保管庫から持ち出して撃ってみました。
そしたら相変わらず不発、弾ポロと絶不調w
これさえ無ければ最高なんですけどね。
ところで再生産を今回購入した人も同様に悩ましい体験をしてるのかと思い、Google検索してみたところあるものを発見しました!
アマゾンでKSC MP9逆輸入バージョンなるものが売っているじゃないですか。
しかも販売元はあの四つ星のお店。
もしやこれってMP9の台湾バージョンつって、システム7とやらになってる奴では??
自分は海外通販でパーツを購入した事は有りますが、銃本体は規制適合性で通関出来るかどうかという問題が有るのを聞いていて、やったことがありません。
でも普通に日本でも買えたんですね(しかもアマゾンで)。
VFCのMP5を買ってお金を一杯使ったばかりだから正直悩みました。
でも手元のMP9を撃てば弾ポロリンで我慢ならず・・・。
買ってしまいましたw
ダークアースバージョン♪
上の奴を塗り替えた訳じゃないですよw
ちゃんと買ったんだから!
しかも再生産の国内バージョンより安いじゃないの!
商品説明には逆輸入バージョンとは書いてあったけど、台湾KWAの箱に入って届くのかと思えばちゃんとKSCの箱に入ってました!
(ダットサイトやHOGUEのグリップスリーブはもちろん自分が後から付けたものです)
しかも日本語のマニュアルが!
でもどうせ既に持ってる国内バージョンと同じものでしょ?
と、思ったら・・・。
あれ?
ちゃんとシステム7仕様に改訂されているじゃん??
ちょ〜っw
パーツリストまで〜。
つかこのパーツ注文してKSCから送ってもらえるんだろうか??
んん?
何か気になる記載が・・・
なんと2010年に既にこのマニュアルは出来ていたと?
日本で販売する予定があったと言う事でしょうか?
なのに何でこの前、旧バージョンを再生産して、システム7は出さないのでしょうか?
判りません・・・。
とにかく2挺めのMP9に目尻が下がりっぱなしの私。
MP5もどこへやらw
肝心の実射性能は?
・・・はっきりいって別物です!
衝撃的に、なんか今までのMP9のリコイルがお子様向けと思えて来るほどガツンガツンきてぶっ壊れるんじゃないかと心配になるほどです!
そして、これまで不満だった給弾系が全て理想的な改良を受けて、これほど痒いところに手が届いた気持ちよさはかつて無いって程にバージョンアップしてました。
過去記事で散々愚痴って来たポイントがもれなく全て改善されていて殆どパーフェクトや〜!!
次回はその点を細かく比較検証して行きます〜。
写真撮りまくりましたので。
2012年09月09日
フルオート出来ない問題
昨日の続きです。
トリガーボックス内のパーツのいくつかをカスタムパーツと交換したら、フルオートが出来ずセミになってしまう問題です。
原因の洗い出しをする為に何度もチェックと組み直しをするはめになりました。

フルオートの作動チェックのおさらいをすると
1、ハンマーを起こします。
2、トリガーを一杯に引きます。
3、トリップレバーを押し込みます。
フルオートだとこれでハンマーが最後まで落ちてファイアリングピンを叩きます。
実際の射撃においてはトリガーを放すまで、1と3を往復するボルトが勝手にやり続ける訳です。
ちなみにセミは3のレバーを押してもハンマーはハーフコックの位置で止まり、もう一度トリガーを引かないとハンマーがファイアリングピンを叩きません。
そのセレクトを、実はセレクターがトリガーの「引きしろ」を変える事で切り替えてます。
つまり途中まで引くとセミ、目一杯引くとフル、引けなくすればセーフと言う訳です。
なのでセレクターを外しても、トリガーを目一杯引けばフルオートのハンマーダウンをテスト出来る訳です。
しかし、このテストを行ってもハンマーはダウンせず、ハーフコックの位置で止まってしまいます!
なぜだ???
というのが前回の問題の内容。

もしやドリルでシアーの穴を貫通させた事が原因では??
あの処理が悪くてプランジャーがシアーに引っ込まなくなって、それでフルオート出来なくなったのかもしれない。
真っ先にその考えが頭に浮かんだので、トリガーボックスを再びバラし、シアーを純正に戻してみました。
すると純正に戻してもフルオートが出来ない事が分かりました。
シアーが原因ではない??
じゃあふたたびシアーをカスタムパーツに換えて、今度はハンマーを純正に戻してみました。
するとまたしてもフルオート出来ませんでした。
ハンマーが原因でもないとすると・・・、あとは自分の組み方が間違っている??
というわけで、今度はハンマーもシアーも純正に戻してみました。
もちろん組み方は同じです。
すると、フルオートしました!
つまり自分の組み方は間違ってない。
ここから言えることは、シアーもハンマーも純正の組み合わせじゃないと不具合が起こるということ。
この辺りで自分も疲れて来て、作業する指も相当痛くなって来てましたが
あるキッカケで原因が見えて来ました。
文字ばっかりでスミマセン。
解けない問題に没頭してると写真を撮ってる余裕が無くなります・・・。

それはハンマーもシアーもBlackTalonの組み合わせに置き換えても、グリップフレームから出してトリガーボックスむき出しで作動チェックするとフルオートが出来るのを発見した事です。
原因はグリップフレームの方にある?

最初に書いたように、セミとフルの切換えはセレクターでトリガーの引きしろを変える事で行っています。
トリガーを一杯まで引けばフルオートになり、グリップフレームの外ではそれが実現した訳ですから
グリップフレームの方にトリガーの引きしろを阻害する要因があるのではと考えました。
例えば矢印の部分がもうすこし広がればトリガーを目一杯引ききる事が出来るのでは?

というわけで、ヤスリで少し削ってみました。
純正ハンマーとシアーの組み合わせでは問題なかったのは、昨日少し触れた、ハンマーのシアーがかかる爪のエッジがスチールだと尖って立っているけど、純正亜鉛はぬるく丸まってるので引っかかりが甘いからではないでしょうか?
しかしグリップフレームの引きしろ加工をしてもまだフルオートが出来ませんでした。
まだ何か原因があるようです・・・ほんと疲れます。
悩みながらあちこちいじって作動チェックを繰り返す・・・。


そのうちまた発見をしました。
トリガーボックスの前部をグリップフレーム内で少し浮かせて作動チェックすると、ハンマーが落ちてフルオートが出来る事が分かったのです。

グリップフレーム内にはトリガーボックスの位置決めをする為の出っ張りが設けられてます。

そしてトリガーボックスの方はその出っ張りが位置する部分に、トリガーを引くとシアーに押されて下がって来る糸巻きみたいなパーツがあります。
この糸巻きみたいなパーツが出っ張りにぶつかって下がりきらず、ぬるい純正ハンマーでは切れていたシアーがスチールだと紙一重で切れずにハンマーを止めてしまったのではないかと。

ようやく見えて来たこの仮説を実証する為に、出っ張りを彫刻刀で削ってみました。
すると不安定ながら改善の手応えがありました!

ならばもう少し削ろう♪

削っては動作確認を繰り返し、満足するまで削ります。
余裕が出て来たので写真も増えて来ました。

そして最後は完全にフルオートが出来るようになったところで、削り痕を綺麗に整えてこうなりました!
ふ〜、もうパパは疲れちゃったよMP5ちゃん。
なに?
スチールハンマーのエッジを純正並みにぬるく削れば早かったのではだって?
それはもし失敗して削り過ぎたら、今度はセミオートが出来なくなって、しかも修正不可能になるリスクがあるじゃないの。
そのまえにドリルでシアーを突き抜いてしまったトラウマがあるんですよ!

というわけで、ちょっとした加工で問題はクリアー出来る事が長い試行錯誤のうえで発見出来ました。
個体差もあるので、同じような問題が誰にでも同様に起きるかは分かりませんが参考になれば幸いです。
ただし、自己責任においてということは言うまでもありませんが・・・。

もう一つ、ついでに。
スチールボルトに換えてからボルトの戻りが悪くなりました。
コッキング後レバーを戻す時に、ゆっくりと手で戻すと途中でボルトが止まってしまいます。

CRUSADER製スチールボルトキャリアは表面がザラザラして滑りが悪いので、すこし滑らかに磨いた方が良さそうです。
特に青い矢印の曲面部は二枚のレバーの上を乗り越える時に抵抗が大きいのでツルツルにしておく方が良さそうです。
亜鉛ボルトだとすぐに擦り減りますが、スチールはさすがに硬くて、なかなかアタリがつきません。
トリガーボックス内のパーツのいくつかをカスタムパーツと交換したら、フルオートが出来ずセミになってしまう問題です。
原因の洗い出しをする為に何度もチェックと組み直しをするはめになりました。
フルオートの作動チェックのおさらいをすると
1、ハンマーを起こします。
2、トリガーを一杯に引きます。
3、トリップレバーを押し込みます。
フルオートだとこれでハンマーが最後まで落ちてファイアリングピンを叩きます。
実際の射撃においてはトリガーを放すまで、1と3を往復するボルトが勝手にやり続ける訳です。
ちなみにセミは3のレバーを押してもハンマーはハーフコックの位置で止まり、もう一度トリガーを引かないとハンマーがファイアリングピンを叩きません。
そのセレクトを、実はセレクターがトリガーの「引きしろ」を変える事で切り替えてます。
つまり途中まで引くとセミ、目一杯引くとフル、引けなくすればセーフと言う訳です。
なのでセレクターを外しても、トリガーを目一杯引けばフルオートのハンマーダウンをテスト出来る訳です。
しかし、このテストを行ってもハンマーはダウンせず、ハーフコックの位置で止まってしまいます!
なぜだ???
というのが前回の問題の内容。
もしやドリルでシアーの穴を貫通させた事が原因では??
あの処理が悪くてプランジャーがシアーに引っ込まなくなって、それでフルオート出来なくなったのかもしれない。
真っ先にその考えが頭に浮かんだので、トリガーボックスを再びバラし、シアーを純正に戻してみました。
すると純正に戻してもフルオートが出来ない事が分かりました。
シアーが原因ではない??
じゃあふたたびシアーをカスタムパーツに換えて、今度はハンマーを純正に戻してみました。
するとまたしてもフルオート出来ませんでした。
ハンマーが原因でもないとすると・・・、あとは自分の組み方が間違っている??
というわけで、今度はハンマーもシアーも純正に戻してみました。
もちろん組み方は同じです。
すると、フルオートしました!
つまり自分の組み方は間違ってない。
ここから言えることは、シアーもハンマーも純正の組み合わせじゃないと不具合が起こるということ。
この辺りで自分も疲れて来て、作業する指も相当痛くなって来てましたが
あるキッカケで原因が見えて来ました。
文字ばっかりでスミマセン。
解けない問題に没頭してると写真を撮ってる余裕が無くなります・・・。
それはハンマーもシアーもBlackTalonの組み合わせに置き換えても、グリップフレームから出してトリガーボックスむき出しで作動チェックするとフルオートが出来るのを発見した事です。
原因はグリップフレームの方にある?
最初に書いたように、セミとフルの切換えはセレクターでトリガーの引きしろを変える事で行っています。
トリガーを一杯まで引けばフルオートになり、グリップフレームの外ではそれが実現した訳ですから
グリップフレームの方にトリガーの引きしろを阻害する要因があるのではと考えました。
例えば矢印の部分がもうすこし広がればトリガーを目一杯引ききる事が出来るのでは?
というわけで、ヤスリで少し削ってみました。
純正ハンマーとシアーの組み合わせでは問題なかったのは、昨日少し触れた、ハンマーのシアーがかかる爪のエッジがスチールだと尖って立っているけど、純正亜鉛はぬるく丸まってるので引っかかりが甘いからではないでしょうか?
しかしグリップフレームの引きしろ加工をしてもまだフルオートが出来ませんでした。
まだ何か原因があるようです・・・ほんと疲れます。
悩みながらあちこちいじって作動チェックを繰り返す・・・。
そのうちまた発見をしました。
トリガーボックスの前部をグリップフレーム内で少し浮かせて作動チェックすると、ハンマーが落ちてフルオートが出来る事が分かったのです。
グリップフレーム内にはトリガーボックスの位置決めをする為の出っ張りが設けられてます。
そしてトリガーボックスの方はその出っ張りが位置する部分に、トリガーを引くとシアーに押されて下がって来る糸巻きみたいなパーツがあります。
この糸巻きみたいなパーツが出っ張りにぶつかって下がりきらず、ぬるい純正ハンマーでは切れていたシアーがスチールだと紙一重で切れずにハンマーを止めてしまったのではないかと。
ようやく見えて来たこの仮説を実証する為に、出っ張りを彫刻刀で削ってみました。
すると不安定ながら改善の手応えがありました!
ならばもう少し削ろう♪
削っては動作確認を繰り返し、満足するまで削ります。
余裕が出て来たので写真も増えて来ました。
そして最後は完全にフルオートが出来るようになったところで、削り痕を綺麗に整えてこうなりました!
ふ〜、もうパパは疲れちゃったよMP5ちゃん。
なに?
スチールハンマーのエッジを純正並みにぬるく削れば早かったのではだって?
それはもし失敗して削り過ぎたら、今度はセミオートが出来なくなって、しかも修正不可能になるリスクがあるじゃないの。
そのまえにドリルでシアーを突き抜いてしまったトラウマがあるんですよ!
というわけで、ちょっとした加工で問題はクリアー出来る事が長い試行錯誤のうえで発見出来ました。
個体差もあるので、同じような問題が誰にでも同様に起きるかは分かりませんが参考になれば幸いです。
ただし、自己責任においてということは言うまでもありませんが・・・。
もう一つ、ついでに。
スチールボルトに換えてからボルトの戻りが悪くなりました。
コッキング後レバーを戻す時に、ゆっくりと手で戻すと途中でボルトが止まってしまいます。
CRUSADER製スチールボルトキャリアは表面がザラザラして滑りが悪いので、すこし滑らかに磨いた方が良さそうです。
特に青い矢印の曲面部は二枚のレバーの上を乗り越える時に抵抗が大きいのでツルツルにしておく方が良さそうです。
亜鉛ボルトだとすぐに擦り減りますが、スチールはさすがに硬くて、なかなかアタリがつきません。
2012年09月09日
MP5のトリガーボックスをいじる
前回ボルトアッセンブリをスチールカスタムパーツと置き換えましたが、今回はトリガーボックス内をいじりました。

今回のカスタムメニューは以下の3点。
・BlackTalon製スチールハンマー
・同じくBT製スチールシアー
・TSC製スチールファイアリングピンセット

その前にトリガーボックスを見まわして、ちょっと気になった点。
矢印の部分はブローバック中、往復するボルトの下部が接する、あるいはかすめる面。
初期ロットではこの面のバリがローディングノズルのガスルート開口部を傷つけると言われていたそうです。
自分が最近購入したこのロットでは、ご覧の通り最初からかなりザックリと表面を削り落としてありました。

ザックリというか、ゴッソリというか、もうネジの頭が半分無くなる程です。
ここまでするか!

反対側。
ちょ〜っ・・・

うっす〜っ!
紙一重。
ここまでやらないと不味いなら、それは設計段階でのミスでしょ。
哀しいのは頭半分無くなったネジ、自分で閉め直したら削り落とされた面がまたちょっとズレましたよ・・・。
しょうがないからネジロックで固定しますけど。

とまあ、話が脇に逸れましたが、今回交換するハンマーを見て行きましょう。
黒い方がBT製スチールハンマーで、もう一つはVFC純正亜鉛ダイキャストハンマー。
寸法は殆ど純正と同じで、重ねてみても全く問題は無さそうです。

BTハンマーは全体ブルーイングで、打撃面だけツルツルに磨かれて銀色の地が出ています。
非常に滑らかで美しい仕上がり。

シアーがかかる爪の部分は鋭くエッジが立っていて、若干ぬるく丸まってる純正とはさすがに違います。
この鋭さが、あとあと自分を苦しめる原因になる訳なんですが・・・、ま、それは後ほど。

お次はシアーです。
最初に見たときから外観が純正と少し異なっていたので心配だったパーツです。
ですが重ねて比較してみると、形状は四角い凹部が丸くなってる以外はピタリと一致しました。
で、真ん中の穴に顔を出しているプランジャーの突出量が純正の半分ぐらいしかありません。
先輩カスタマーの話によれば、このプランジャーが十分に突出してないとセミで撃ってもフルオートになってしまうそうです。


さて形状の異なる部分ですが、トリガーと組み合わせてみたところ、特に干渉する事は無いようでした。
となると、BT製の形状の方がより強度が増してむしろ結構なんじゃないかと。

それではプランジャーの突出量を調整します。
一番上のちっこいのがプランジャーで、シアー内部に開いた穴に収まり、後ろからスプリング、そして割りピンで抜け止めされてます。
その穴が浅いため、さらに深く掘る訳ですが相手はスチール!
最初は二段目のダイヤモンドビットで慎重に進めていたんですが、一向にらちがあきません。
もう疲れて、次は下のドリルビットでやってみる事に。

そしたら・・・あっ、という瞬間に・・・。
やばい、突き抜けてしまった・・・(oдО;|||)タラー
ダイヤモンドビットと違って、ドリルの潜り込んで行く性質を忘れていた。

恐る恐るプランジャーを差し込んでみたら、抜け落ちるすんでのところで引っかかってました。
ドリルが貫通した瞬間に「あっ」と驚いて手を離したおかげで、穴の最後の縁のところを掻き取られる前に済んだようで、わずかに引っかかりが残ってました。

まあ、もし仮にプランジャーが抜け落ちたとしても、実際組んだときはこのようにトリガーピンがハマるので抜け防止になって、機能的に問題はないでしょう。
ただし組み立て時はちょっと面倒になると思いますが。

にしても良かった良かった。
一瞬落ち込みかけたけどw

交換後の純正パーツはジップロックにカスタムパーツのタグと一緒にして保存。
ファイアリングピンですが、写真を取り忘れてしまったのですが、もう一切問題無しなので省略します。
さて、無事交換が終って(最初の写真)本体に収納し、実写テストをしました。
ところがそこで問題発生!
なんとフルオートが出来なくなった!!
セミ、問題無し、フル・・・あれ? 一発だけ?
ていうか、これセミそのものじゃん。

おかしいので再びバラして検証します。
フルオートが正しく機能するかを調べる為に上の写真のような事をします。
1、ハンマーを起こします。
2、トリガーを一杯に引きます。
3、トリップレバーを押し込みます。
フルオートだとこれでハンマーが最後まで落ちてファイアリングピンを叩きます。
その後はトリガーを放すまで、1と3を往復するボルトが勝手にやり続ける訳です。
ちなみにセミは3のレバーを押してもハンマーはハーフコックの位置で止まり、もう一度トリガーを引かないとハンマーがファイアリングピンを叩きません。
そのセレクトを、実はセレクターがトリガーの「引きしろ」を変える事で切り替えてます。
つまり途中まで引くとセミ、目一杯引くとフル、引けなくすればセーフと言う訳です。
なのでセレクターを外しても、トリガーを目一杯引けばフルオートのハンマーダウンをテスト出来る訳です。
しかし、このテストを行ってもハンマーはダウンせず、ハーフコックの位置で止まってしまいます!
なぜだ???
一瞬脳裏に甦ったドリルでの貫通・・・(汗
でも結論から言えばそれは関係ありません。
それはハンマーのあのエッジの立った爪が問題だったのでした・・・・。
ごめんなさい、疲れたので今日はここまでw
次回、問題の発見と解決までの試行錯誤をアップしますw

やっぱ最後にこれがないと。
今回のカスタムメニューは以下の3点。
・BlackTalon製スチールハンマー
・同じくBT製スチールシアー
・TSC製スチールファイアリングピンセット
その前にトリガーボックスを見まわして、ちょっと気になった点。
矢印の部分はブローバック中、往復するボルトの下部が接する、あるいはかすめる面。
初期ロットではこの面のバリがローディングノズルのガスルート開口部を傷つけると言われていたそうです。
自分が最近購入したこのロットでは、ご覧の通り最初からかなりザックリと表面を削り落としてありました。
ザックリというか、ゴッソリというか、もうネジの頭が半分無くなる程です。
ここまでするか!
反対側。
ちょ〜っ・・・
うっす〜っ!
紙一重。
ここまでやらないと不味いなら、それは設計段階でのミスでしょ。
哀しいのは頭半分無くなったネジ、自分で閉め直したら削り落とされた面がまたちょっとズレましたよ・・・。
しょうがないからネジロックで固定しますけど。
とまあ、話が脇に逸れましたが、今回交換するハンマーを見て行きましょう。
黒い方がBT製スチールハンマーで、もう一つはVFC純正亜鉛ダイキャストハンマー。
寸法は殆ど純正と同じで、重ねてみても全く問題は無さそうです。
BTハンマーは全体ブルーイングで、打撃面だけツルツルに磨かれて銀色の地が出ています。
非常に滑らかで美しい仕上がり。
シアーがかかる爪の部分は鋭くエッジが立っていて、若干ぬるく丸まってる純正とはさすがに違います。
この鋭さが、あとあと自分を苦しめる原因になる訳なんですが・・・、ま、それは後ほど。
お次はシアーです。
最初に見たときから外観が純正と少し異なっていたので心配だったパーツです。
ですが重ねて比較してみると、形状は四角い凹部が丸くなってる以外はピタリと一致しました。
で、真ん中の穴に顔を出しているプランジャーの突出量が純正の半分ぐらいしかありません。
先輩カスタマーの話によれば、このプランジャーが十分に突出してないとセミで撃ってもフルオートになってしまうそうです。
さて形状の異なる部分ですが、トリガーと組み合わせてみたところ、特に干渉する事は無いようでした。
となると、BT製の形状の方がより強度が増してむしろ結構なんじゃないかと。
それではプランジャーの突出量を調整します。
一番上のちっこいのがプランジャーで、シアー内部に開いた穴に収まり、後ろからスプリング、そして割りピンで抜け止めされてます。
その穴が浅いため、さらに深く掘る訳ですが相手はスチール!
最初は二段目のダイヤモンドビットで慎重に進めていたんですが、一向にらちがあきません。
もう疲れて、次は下のドリルビットでやってみる事に。
そしたら・・・あっ、という瞬間に・・・。
やばい、突き抜けてしまった・・・(oдО;|||)タラー
ダイヤモンドビットと違って、ドリルの潜り込んで行く性質を忘れていた。
恐る恐るプランジャーを差し込んでみたら、抜け落ちるすんでのところで引っかかってました。
ドリルが貫通した瞬間に「あっ」と驚いて手を離したおかげで、穴の最後の縁のところを掻き取られる前に済んだようで、わずかに引っかかりが残ってました。
まあ、もし仮にプランジャーが抜け落ちたとしても、実際組んだときはこのようにトリガーピンがハマるので抜け防止になって、機能的に問題はないでしょう。
ただし組み立て時はちょっと面倒になると思いますが。
にしても良かった良かった。
一瞬落ち込みかけたけどw
交換後の純正パーツはジップロックにカスタムパーツのタグと一緒にして保存。
ファイアリングピンですが、写真を取り忘れてしまったのですが、もう一切問題無しなので省略します。
さて、無事交換が終って(最初の写真)本体に収納し、実写テストをしました。
ところがそこで問題発生!
なんとフルオートが出来なくなった!!
セミ、問題無し、フル・・・あれ? 一発だけ?
ていうか、これセミそのものじゃん。
おかしいので再びバラして検証します。
フルオートが正しく機能するかを調べる為に上の写真のような事をします。
1、ハンマーを起こします。
2、トリガーを一杯に引きます。
3、トリップレバーを押し込みます。
フルオートだとこれでハンマーが最後まで落ちてファイアリングピンを叩きます。
その後はトリガーを放すまで、1と3を往復するボルトが勝手にやり続ける訳です。
ちなみにセミは3のレバーを押してもハンマーはハーフコックの位置で止まり、もう一度トリガーを引かないとハンマーがファイアリングピンを叩きません。
そのセレクトを、実はセレクターがトリガーの「引きしろ」を変える事で切り替えてます。
つまり途中まで引くとセミ、目一杯引くとフル、引けなくすればセーフと言う訳です。
なのでセレクターを外しても、トリガーを目一杯引けばフルオートのハンマーダウンをテスト出来る訳です。
しかし、このテストを行ってもハンマーはダウンせず、ハーフコックの位置で止まってしまいます!
なぜだ???
一瞬脳裏に甦ったドリルでの貫通・・・(汗
でも結論から言えばそれは関係ありません。
それはハンマーのあのエッジの立った爪が問題だったのでした・・・・。
ごめんなさい、疲れたので今日はここまでw
次回、問題の発見と解決までの試行錯誤をアップしますw
やっぱ最後にこれがないと。
2012年09月03日
追加のパーツが来た!
久しぶりに雨が降ったりして良いお湿りの日曜日。
香港から追加のパーツが来た♪

アレのそれですなw
何故か箱が裏返しになってるのはどういうことなんだろ?
香港のショップの習慣なのか?
台湾の製品を香港から買うというのも無駄に輸送コストかかってるよね。

もう一つがコレ。
TSCのスチールファイアリングピン。

でもってコレも。
TSCのアルミローディングノズル。
SGWさんのオススメで注文しました。

アルミローディングノズルが来たので、いよいよボルトを交換出来ます。
前回入手したCRUSADER製スチールボルトキャリアとBlack Talon製ボルトヘッドは、まだ袋に入ったまま開封すらしてません。
本当は届いたらさっさと検品しとくべきでしょうけどね。

てか、純正ボルトの摩耗が凄い。
購入してからまだ100発も撃ってないはずですが、この減り具合はヤバいね。
マガジンのガスルートパッキンが千切れるのも酷いですがw(前記事参照)

しかも既にジャムってノズル先端が歪んでしまってます。
まあそのせいもあって、今回のアルミノズル導入なわけですが。

左、純正プラ。
右、アルミ。
比べてみると純正プラの方がエッジが立ってて角張ってるのに対し、アルミ削り出しの方が丸みがあってソフトな感じに見えます。
アルミはしかも塗装だし。

BB弾を蹴り出す突起部もアルミの方は下部を丸めてあります。
アルミの強度があれば先端が薄くなっても問題は無いでしょう。

左右の位置が入れ替わりますが、右のプラノズルが弾を噛んだことで少し変形しています。
重さに関しては、やはりアルミの方はそれなりに来る感じ。
公式には20gということで純正の4倍ぐらい重いかも。
とはいえ、ものすごく小さい数字のところでの4倍ですからそんなに心配は無いかも。
ノズルリターンスプリングがへたるのが早まるかな?

こういう感じで純正部品とのチャンポンになる訳ですが、ここで最初のハードルが!
真ん中の負圧バルブがキツくて中に入りません(;´▽`A``
このバルブは発射側とブローバック側のガスの切換えを瞬時に行う繊細な切換え弁なので、本来スルッと苦もなくノズル内部に滑り込まなくては行けません。

外側を削って細めてやらなくてはなりません。
耐水ペーパーを巻き付けて手作業で削ってましたが、一向に埒があかんのう。

電動あじゃすたぶるドリルワークで一気に剥くべし。
このあたりで既に上級者レベルの作業内容になってきました。
自信の無い人はその道の人にお願いした方が良いでしょう。

そうそう、忘れていましたがMP5の日本発売バージョンには低圧ガス用のノズルスプリングがオマケで付いていました。
この機会にこのスプリングに置き換えて組み込みましょう。

ジャパンバージョンのスプリングは見た目にも全然違うし、手で触っても反発がフニャフニャに弱いです。
これによって低圧ガスでも負圧バルブの切換えがスピーディーになるので、是非交換しておきたいパーツ。

おっと、組み込む前にアルミノズル側も少し手を入れておこう。
BB弾を蹴り出す突起部は既に角を丸めてありますが、ガスルート開口部の前側の角も少し丸めておきます。
どうもこの部分もマガジンのパッキンに引っ掛ける疑いが濃いので。

さていよいよ、スチールボルトの登場です!
CRUSADER製スチールボルトキャリアにBlack Talon製のシリンダーをぶっ刺す訳ですが、この組み合わせでシリンダーがキツくハマって動かなくなり、結局ぶっ壊さなきゃならなくなった人の記事を読みましたので、あらかじめシリンダーの外周を削っておきます。
あとはプラハンで叩き込む訳ですが、間にカマボコ板かなんかを当てて打撃が一点に集中しないようにしましょう。

と、またまたその前にスチールボルトをよく見ると結構油に混じってゴミがついてるので、いったん脱脂洗浄してオイルを吹き直そうかと。
そしたら油に濡れて気付きにくかった赤錆が、脱脂した事でアラワになりました。
これは取り除いてブルーイングし直さないと!

あーだこーだ時間がかかる作業の果てに、ようやくボルトが組み上がりました。
CRUSADER製スチールボルトキャリアにBlack Talon製ボルトヘッド・シリンダー、そしてTSC製アルミノズル。
完璧な組み上がりです。
シリンダーの剥いた部分がボルト挿入部に対して、5mmほど剥かずに残してるのが実はミソです。
純正ボルトキャリアはボルトヘッドの位置決めをする為に、後ろから芋ネジで固定するのですが、CRUSADER製にはそのネジ穴がありません。
差し込んだシリンダーの摩擦抵抗だけでボルトヘッドが定位置に留まっていなきゃいけないので、シリンダーを削り過ぎて緩くなると今度は困った事になってしまうのです。
5mmの幅はその為の保険と言う訳です。

本体に収めてみました。
やはりこのボルトの溶接痕がないとね。

フレーム下部より覗き込んだ図。
Black Talonの刻印がちょっと見えてます。
そして試射。
若干ボルトの動作が遅くなった。
まだアタリが取れてない感じですが、ちゃんと問題なく作動したので大成功♪

今日はボルトの交換だけで体力を使い果たしたので、他のパーツはまた後日にやろう。
ストック換えたらMP5がナニコレ、ちっさくなっちゃった!
すげえ〜こんなに小さいんだ!!
まるで別物だな。
ストックは気分で換えられるよう、ぜひ固定と両方持ってたいね。
香港から追加のパーツが来た♪
アレのそれですなw
何故か箱が裏返しになってるのはどういうことなんだろ?
香港のショップの習慣なのか?
台湾の製品を香港から買うというのも無駄に輸送コストかかってるよね。
もう一つがコレ。
TSCのスチールファイアリングピン。
でもってコレも。
TSCのアルミローディングノズル。
SGWさんのオススメで注文しました。
アルミローディングノズルが来たので、いよいよボルトを交換出来ます。
前回入手したCRUSADER製スチールボルトキャリアとBlack Talon製ボルトヘッドは、まだ袋に入ったまま開封すらしてません。
本当は届いたらさっさと検品しとくべきでしょうけどね。
てか、純正ボルトの摩耗が凄い。
購入してからまだ100発も撃ってないはずですが、この減り具合はヤバいね。
マガジンのガスルートパッキンが千切れるのも酷いですがw(前記事参照)
しかも既にジャムってノズル先端が歪んでしまってます。
まあそのせいもあって、今回のアルミノズル導入なわけですが。
左、純正プラ。
右、アルミ。
比べてみると純正プラの方がエッジが立ってて角張ってるのに対し、アルミ削り出しの方が丸みがあってソフトな感じに見えます。
アルミはしかも塗装だし。
BB弾を蹴り出す突起部もアルミの方は下部を丸めてあります。
アルミの強度があれば先端が薄くなっても問題は無いでしょう。
左右の位置が入れ替わりますが、右のプラノズルが弾を噛んだことで少し変形しています。
重さに関しては、やはりアルミの方はそれなりに来る感じ。
公式には20gということで純正の4倍ぐらい重いかも。
とはいえ、ものすごく小さい数字のところでの4倍ですからそんなに心配は無いかも。
ノズルリターンスプリングがへたるのが早まるかな?
こういう感じで純正部品とのチャンポンになる訳ですが、ここで最初のハードルが!
真ん中の負圧バルブがキツくて中に入りません(;´▽`A``
このバルブは発射側とブローバック側のガスの切換えを瞬時に行う繊細な切換え弁なので、本来スルッと苦もなくノズル内部に滑り込まなくては行けません。
外側を削って細めてやらなくてはなりません。
耐水ペーパーを巻き付けて手作業で削ってましたが、一向に埒があかんのう。
電動あじゃすたぶるドリルワークで一気に剥くべし。
このあたりで既に上級者レベルの作業内容になってきました。
自信の無い人はその道の人にお願いした方が良いでしょう。
そうそう、忘れていましたがMP5の日本発売バージョンには低圧ガス用のノズルスプリングがオマケで付いていました。
この機会にこのスプリングに置き換えて組み込みましょう。
ジャパンバージョンのスプリングは見た目にも全然違うし、手で触っても反発がフニャフニャに弱いです。
これによって低圧ガスでも負圧バルブの切換えがスピーディーになるので、是非交換しておきたいパーツ。
おっと、組み込む前にアルミノズル側も少し手を入れておこう。
BB弾を蹴り出す突起部は既に角を丸めてありますが、ガスルート開口部の前側の角も少し丸めておきます。
どうもこの部分もマガジンのパッキンに引っ掛ける疑いが濃いので。
さていよいよ、スチールボルトの登場です!
CRUSADER製スチールボルトキャリアにBlack Talon製のシリンダーをぶっ刺す訳ですが、この組み合わせでシリンダーがキツくハマって動かなくなり、結局ぶっ壊さなきゃならなくなった人の記事を読みましたので、あらかじめシリンダーの外周を削っておきます。
あとはプラハンで叩き込む訳ですが、間にカマボコ板かなんかを当てて打撃が一点に集中しないようにしましょう。
と、またまたその前にスチールボルトをよく見ると結構油に混じってゴミがついてるので、いったん脱脂洗浄してオイルを吹き直そうかと。
そしたら油に濡れて気付きにくかった赤錆が、脱脂した事でアラワになりました。
これは取り除いてブルーイングし直さないと!
あーだこーだ時間がかかる作業の果てに、ようやくボルトが組み上がりました。
CRUSADER製スチールボルトキャリアにBlack Talon製ボルトヘッド・シリンダー、そしてTSC製アルミノズル。
完璧な組み上がりです。
シリンダーの剥いた部分がボルト挿入部に対して、5mmほど剥かずに残してるのが実はミソです。
純正ボルトキャリアはボルトヘッドの位置決めをする為に、後ろから芋ネジで固定するのですが、CRUSADER製にはそのネジ穴がありません。
差し込んだシリンダーの摩擦抵抗だけでボルトヘッドが定位置に留まっていなきゃいけないので、シリンダーを削り過ぎて緩くなると今度は困った事になってしまうのです。
5mmの幅はその為の保険と言う訳です。
本体に収めてみました。
やはりこのボルトの溶接痕がないとね。
フレーム下部より覗き込んだ図。
Black Talonの刻印がちょっと見えてます。
そして試射。
若干ボルトの動作が遅くなった。
まだアタリが取れてない感じですが、ちゃんと問題なく作動したので大成功♪
今日はボルトの交換だけで体力を使い果たしたので、他のパーツはまた後日にやろう。
ストック換えたらMP5がナニコレ、ちっさくなっちゃった!
すげえ〜こんなに小さいんだ!!
まるで別物だな。
ストックは気分で換えられるよう、ぜひ固定と両方持ってたいね。