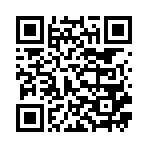2020年09月12日
小さいことは良いことだ?
灼熱のピークは過ぎたのでしょうか、これからは台風の季節か?
先日の台風10号、関東には直接影響はなかったのですが、晴れているのに雷鳴、青い空がうっすら見えてるのに土砂降り、1日のうちにコロコロ空模様が変わる変な感じでした。


ウエスタンアームズのベレッタM1934を自分でビンテージ風に仕上げ直した物です。
もともとは中古で8千円ぐらいで手に入れた、相当くたびれたパーカー塗装のミリタリーバージョン。
ビンテージだけどイタリアっぽくお洒落な感じにできないかなと思って塗装しましたね。

ポイントはブローバックで前後するスライドによって表面が擦れたというのを再現したアウターバレル。
これは実銃の写真を参考にしてやったような気がします。
言い忘れましたが、この仕上げ直しをやったのもずいぶん昔のことなので、過去記事でその時のことはすでに紹介済みのエアガンです。
このモデルの好きなところは、ポケットに入るような小さなオートでありながら、手にとれば見た目にそぐわぬ重量感と、バラせばわかるプラパーツのなかなかの厚みによる剛性感。
そしてマグナブローバックによる瞬発力のあるブローバック。
更にテイクダウンがすごく簡単な設計・構造、あとは見た目の美しさ・デザインです。


先日中古サイトで昔のフィルム一眼レフカメラのOLYMPUS OM-1が入荷したのを偶然見つけ、美品という説明と様々な角度からの商品写真を眺めてるうちにムラムラと来てポチってしまいました。
特に古いカメラというのはモデルガンなどと比べるとはるかに実用品としての使用歴があるので、美品と言われてもそれだけの年代物にしてはということになる場合がほとんどです。
しかしちゃんとした中古カメラ店で購入すれば、ジャンクでなければ実用上問題がなく、一定期間の保証もついていたりします。
そして届いたカメラは、購入価格相応に傷みの少ない美品で、しかもオーバーホール済みということで、不具合は一切ありませんでした。


そのOLYMPUS OM-1というカメラは1972年の発売当時、他社の一眼レフカメラと比べてあり得ないほど小型軽量でありながら、機能的にも新しい技術を盛り込んだ妥協のない製品でした。
当時の制作秘話を語った記事をネットで見つけることができますが、そのことが評価をされ、この度、国立科学博物館の「未来技術遺産」に登録されました。



若い頃はなんでも最先端の物が好きで、古くなったものはパッパと捨て去ることが “クールな俺” 的に思っていました。
でもその自分自身が古くなってくると、昔のフィルムカメラや、もう中古でしか手に入らないモデルガンなどに何とも言えない愛着と当時の技術へのリスペクトが湧いてきます。
現存するだけ、時間と共にどんどん朽ちて壊れて消えていく物たちに愛が湧くのです。
先日の台風10号、関東には直接影響はなかったのですが、晴れているのに雷鳴、青い空がうっすら見えてるのに土砂降り、1日のうちにコロコロ空模様が変わる変な感じでした。


ウエスタンアームズのベレッタM1934を自分でビンテージ風に仕上げ直した物です。
もともとは中古で8千円ぐらいで手に入れた、相当くたびれたパーカー塗装のミリタリーバージョン。
ビンテージだけどイタリアっぽくお洒落な感じにできないかなと思って塗装しましたね。

ポイントはブローバックで前後するスライドによって表面が擦れたというのを再現したアウターバレル。
これは実銃の写真を参考にしてやったような気がします。
言い忘れましたが、この仕上げ直しをやったのもずいぶん昔のことなので、過去記事でその時のことはすでに紹介済みのエアガンです。
このモデルの好きなところは、ポケットに入るような小さなオートでありながら、手にとれば見た目にそぐわぬ重量感と、バラせばわかるプラパーツのなかなかの厚みによる剛性感。
そしてマグナブローバックによる瞬発力のあるブローバック。
更にテイクダウンがすごく簡単な設計・構造、あとは見た目の美しさ・デザインです。


先日中古サイトで昔のフィルム一眼レフカメラのOLYMPUS OM-1が入荷したのを偶然見つけ、美品という説明と様々な角度からの商品写真を眺めてるうちにムラムラと来てポチってしまいました。
特に古いカメラというのはモデルガンなどと比べるとはるかに実用品としての使用歴があるので、美品と言われてもそれだけの年代物にしてはということになる場合がほとんどです。
しかしちゃんとした中古カメラ店で購入すれば、ジャンクでなければ実用上問題がなく、一定期間の保証もついていたりします。
そして届いたカメラは、購入価格相応に傷みの少ない美品で、しかもオーバーホール済みということで、不具合は一切ありませんでした。


そのOLYMPUS OM-1というカメラは1972年の発売当時、他社の一眼レフカメラと比べてあり得ないほど小型軽量でありながら、機能的にも新しい技術を盛り込んだ妥協のない製品でした。
当時の制作秘話を語った記事をネットで見つけることができますが、そのことが評価をされ、この度、国立科学博物館の「未来技術遺産」に登録されました。



若い頃はなんでも最先端の物が好きで、古くなったものはパッパと捨て去ることが “クールな俺” 的に思っていました。
でもその自分自身が古くなってくると、昔のフィルムカメラや、もう中古でしか手に入らないモデルガンなどに何とも言えない愛着と当時の技術へのリスペクトが湧いてきます。
現存するだけ、時間と共にどんどん朽ちて壊れて消えていく物たちに愛が湧くのです。
2016年02月25日
ベレッタコンパクト
ベレッタM84FSとM1934のカーボンブラック。

どちらもWAのカーボンブラックモデルで、黒染め等の処理がされてない物である。
一応ブラスト&ポリッシュという処理はされているらしいが。
自分はこのカーボンブラックモデルが結構好きで、初めて見たときは素材の成型ムラのようなものに戸惑ったが、今ではそれも良い味をだしてるように見えている。

このM1934もフレームのセフティレバー付近にムラがある。
この個体は購入してから随分経つが、過去に2回ほど本体平面部をポリッシュし直していたりして、購入当時とはまた違った雰囲気になっている。

ちなみに購入当時はこんな感じだった。

こうして並べるとM84FSが小さなM1934に匹敵するぐらいコンパクトになってるのが分かる。
ダブルカアラムのため、シングルのM1934よりグリップ周りはずっと太いが。

M1934のメタルグリップはつい先日、枠の部分だけポリッシュして酸化皮膜を少し落とした。
いつかWAのリアルスチールモデルを真似して自分のもリアル化しようと思っていた。
雰囲気はかなり良くなった。

M84FSのアウターバレルもポリッシュしてみた。
少しだけ金属光沢が強まっている。
アウターバレルについていた染みのようなものが落とせるかと思ったのだが、

やっぱり落ちなかった。
でも金属光沢が強まった分、少し目立ちにくくなっただろうか?
黒くブルーイングすればもっと目立たなくできそうだ。

やっぱりカーボンブラックは良い。
樹脂でありながら金属的な重厚感がたまらない。
手入れが悪いと黒ずむとか、心配要素があるが、そうなってからポリッシュすることでまた元と違った雰囲気に仕上げ直したりできるのも魅力に感じる。

どちらもWAのカーボンブラックモデルで、黒染め等の処理がされてない物である。
一応ブラスト&ポリッシュという処理はされているらしいが。
自分はこのカーボンブラックモデルが結構好きで、初めて見たときは素材の成型ムラのようなものに戸惑ったが、今ではそれも良い味をだしてるように見えている。
このM1934もフレームのセフティレバー付近にムラがある。
この個体は購入してから随分経つが、過去に2回ほど本体平面部をポリッシュし直していたりして、購入当時とはまた違った雰囲気になっている。
ちなみに購入当時はこんな感じだった。
こうして並べるとM84FSが小さなM1934に匹敵するぐらいコンパクトになってるのが分かる。
ダブルカアラムのため、シングルのM1934よりグリップ周りはずっと太いが。
M1934のメタルグリップはつい先日、枠の部分だけポリッシュして酸化皮膜を少し落とした。
いつかWAのリアルスチールモデルを真似して自分のもリアル化しようと思っていた。
雰囲気はかなり良くなった。
M84FSのアウターバレルもポリッシュしてみた。
少しだけ金属光沢が強まっている。
アウターバレルについていた染みのようなものが落とせるかと思ったのだが、
やっぱり落ちなかった。
でも金属光沢が強まった分、少し目立ちにくくなっただろうか?
黒くブルーイングすればもっと目立たなくできそうだ。
やっぱりカーボンブラックは良い。
樹脂でありながら金属的な重厚感がたまらない。
手入れが悪いと黒ずむとか、心配要素があるが、そうなってからポリッシュすることでまた元と違った雰囲気に仕上げ直したりできるのも魅力に感じる。
2011年05月02日
ビンテージ風M1934完成ショット
中古価格¥5600-で入手したWAベレッタM1934ミルスペック。
こんな値段で売られるなんて、元はいくらで買い取られた娘なんでしょ?( *´Д⊂ グスン…
そんな不憫な個体が仕上げ直しによりビンテージ風に生まれ変わりました。
本日ついに完成披露いたします!
(ドラムロール)
どうぞご覧ください。









ランヤードリングの内側が釣り紐で擦れたような感じになってます。





グリップ後部は右手で握りしめた時に一番擦れそうな、親指の関節のところと掌底が当たるところを剥げた感じにしてみました。




カーボンブラックモデルは表面の手入れをサボっていたせいか、すっかり黒くなってしまって今では無塗装のABS感しか漂わなくなってしまった・・・。



以上です。
完成してしまうと何かスッポリ抜けたような寂しさが残ります。
こうしてみるとホワイトグリップが映えますね。
背景を黒にすると、写真がプロっぽくなるのでイイ!

今回の撮影に使用してるカメラはいつものサイバーショットDSC-T9(2005年購入)。
いつもはそのまま手に持っての撮影ですが、今回は後ろの安っぽい三脚を使って頑張って撮影しました。
こんな値段で売られるなんて、元はいくらで買い取られた娘なんでしょ?( *´Д⊂ グスン…
そんな不憫な個体が仕上げ直しによりビンテージ風に生まれ変わりました。
本日ついに完成披露いたします!
(ドラムロール)
どうぞご覧ください。
ランヤードリングの内側が釣り紐で擦れたような感じになってます。
グリップ後部は右手で握りしめた時に一番擦れそうな、親指の関節のところと掌底が当たるところを剥げた感じにしてみました。
カーボンブラックモデルは表面の手入れをサボっていたせいか、すっかり黒くなってしまって今では無塗装のABS感しか漂わなくなってしまった・・・。
以上です。
完成してしまうと何かスッポリ抜けたような寂しさが残ります。
こうしてみるとホワイトグリップが映えますね。
背景を黒にすると、写真がプロっぽくなるのでイイ!

今回の撮影に使用してるカメラはいつものサイバーショットDSC-T9(2005年購入)。
いつもはそのまま手に持っての撮影ですが、今回は後ろの安っぽい三脚を使って頑張って撮影しました。
2011年05月01日
ホワイトグリップ
中古格安で買ったベレッタM1934の仕上げ直し、残すところ後二回になりました。
今回はメタルグリップの仕上げ直しです。

以前塗装を剥離しておいたグリップですが、どんなイメージにしようかルンルン♪としていたところ、よっしーさんからのアイディア提供もありブルーイングと塗装の合わせ業で仕上げる事にしました。

今回塗装に使うのはこちら、カンペ大先生のところのシリコンラッカースプレーです♪
どんな塗料かって、ガン用じゃなく日用多目的ないわゆるホムセンスプレーってやつですね。
値段は300mlでなんと、¥580-(ユニディ)だっw やすっ!
しかし安かろう悪かろうでは有りませんよ。
アクリルシリコン樹脂により、耐候性・耐久性にすぐれた強固な被膜で定評があるらしい。
色はホワイトですよん。

最初に枠の部分をブルーイングしてからマスキングして、ミッチャクロン、そして白塗装です。
なかなか光沢感があって良い仕上がり♪
マスキングを剥がすと塗料の端が切れずに残ってしまうので、ルーペを覗きながら慎重に針で切るように取り除きます。

この境界線が奇麗に決まると、まるで実銃のようにスチール部と樹脂部が別パーツで出来てるように見える!
というのが、よっしーさんのアイディアですw

続いてメダリオンを貼付ける準備です。
使用するのはこちらの両面粘着シート。
厚さ1.2mmのスポンジシートに接着剤が付いてて、任意の形にカットして使います。
この場合メダリオンのサイズ。
ちゃっちゃと貼ろうか〜
と思ったんですが、このままだと奇麗過ぎてイマイチビンテージ仕上げに似合わない気がしてきた。

ってことで、メダリオンにも銀塗装+黒塗装(銃 I)+エイジング処理。
ウ〜ン、なんかどっかで見たような感じ。
あ、金色だったら学ランのボタンじゃんw

んじゃ貼りまっせ〜。
おお、やっぱりこっちの方が良いねえ〜。

メダリオンを入れる時の角度は実銃の写真を参考に。
どうやらPBの縦軸がグリップの前側のラインと平行になるのが正解らしい。
最近WAはこの辺がテキトーになっちゃってるみたい。
さて、グリップも完成し、いよいよ次回はシリーズ最終回。
ビンテージベレッタM1934のお姿をたっぷり公開します。
写真は気合いを入れて、ちゃんと三脚立てて撮影しますからね〜。
今回はメタルグリップの仕上げ直しです。
以前塗装を剥離しておいたグリップですが、どんなイメージにしようかルンルン♪としていたところ、よっしーさんからのアイディア提供もありブルーイングと塗装の合わせ業で仕上げる事にしました。
今回塗装に使うのはこちら、カンペ大先生のところのシリコンラッカースプレーです♪
どんな塗料かって、ガン用じゃなく日用多目的ないわゆるホムセンスプレーってやつですね。
値段は300mlでなんと、¥580-(ユニディ)だっw やすっ!
しかし安かろう悪かろうでは有りませんよ。
アクリルシリコン樹脂により、耐候性・耐久性にすぐれた強固な被膜で定評があるらしい。
色はホワイトですよん。
最初に枠の部分をブルーイングしてからマスキングして、ミッチャクロン、そして白塗装です。
なかなか光沢感があって良い仕上がり♪
マスキングを剥がすと塗料の端が切れずに残ってしまうので、ルーペを覗きながら慎重に針で切るように取り除きます。
この境界線が奇麗に決まると、まるで実銃のようにスチール部と樹脂部が別パーツで出来てるように見える!
というのが、よっしーさんのアイディアですw
続いてメダリオンを貼付ける準備です。
使用するのはこちらの両面粘着シート。
厚さ1.2mmのスポンジシートに接着剤が付いてて、任意の形にカットして使います。
この場合メダリオンのサイズ。
ちゃっちゃと貼ろうか〜
と思ったんですが、このままだと奇麗過ぎてイマイチビンテージ仕上げに似合わない気がしてきた。
ってことで、メダリオンにも銀塗装+黒塗装(銃 I)+エイジング処理。
ウ〜ン、なんかどっかで見たような感じ。
あ、金色だったら学ランのボタンじゃんw
んじゃ貼りまっせ〜。
おお、やっぱりこっちの方が良いねえ〜。
メダリオンを入れる時の角度は実銃の写真を参考に。
どうやらPBの縦軸がグリップの前側のラインと平行になるのが正解らしい。
最近WAはこの辺がテキトーになっちゃってるみたい。
さて、グリップも完成し、いよいよ次回はシリーズ最終回。
ビンテージベレッタM1934のお姿をたっぷり公開します。
写真は気合いを入れて、ちゃんと三脚立てて撮影しますからね〜。
2011年04月29日
ビンテージ仕上げ
中古格安で買ったベレッタM1934の仕上げ直し、まだまだ進行中です。
今回はアウターバレルの仕上げ直し。
前回エイジング処理で古ぼけた外観になった本体の塗装に合わせて、アウターバレルもやはり同様に古ぼけた感じにしないと・・・って訳で。

どちらも自分でブルーイングしたM1934のです。
下が今回ビンテージ仕上げにした方。

作業工程は省略しますが、上のような状態からサンドペーパー、スポンジヤスリなどを使って下のような状態にしています。

ブローバックでスライドと擦れる部分を特に強く被膜を剥いでいます。
実銃もだいたいこんな感じですが、実際の使用による剥げと、サンドペーパーで模して付けた剥げでは似せるにしても限界がありますから、まああまり厳しい目で見ないどいてくださいw
このバレルを前回のエイジング処理したスライドに仮合わせしてみたら、あまりにもヤバすぎて最終発表まで公開出来ません。
期待して待っててくださいね〜♪
今回はアウターバレルの仕上げ直し。
前回エイジング処理で古ぼけた外観になった本体の塗装に合わせて、アウターバレルもやはり同様に古ぼけた感じにしないと・・・って訳で。
どちらも自分でブルーイングしたM1934のです。
下が今回ビンテージ仕上げにした方。
作業工程は省略しますが、上のような状態からサンドペーパー、スポンジヤスリなどを使って下のような状態にしています。
ブローバックでスライドと擦れる部分を特に強く被膜を剥いでいます。
実銃もだいたいこんな感じですが、実際の使用による剥げと、サンドペーパーで模して付けた剥げでは似せるにしても限界がありますから、まああまり厳しい目で見ないどいてくださいw
このバレルを前回のエイジング処理したスライドに仮合わせしてみたら、あまりにもヤバすぎて最終発表まで公開出来ません。
期待して待っててくださいね〜♪
2011年04月26日
エイジング処理
2011年04月23日
偽鉄塗装M1934
中古格安で買ったベレッタM1934の仕上げ直し、今日も進行中です。
今回はフレーム・スライドの塗装のその後。

一度全体をシルバーに塗装した後、黒系の塗料で薄く上塗りしました。
下にシルバーがあるせいで、上塗りに濃淡をつけたとき薄いところではシルバーが透けて見えます。
その雰囲気が普通に塗装した場合より、俄然金属感が現れるので気に入ってます。
今回はまだ吹きっぱなしの状態ですが、ここから更にスポンジヤスリなどでエッジを擦ってシルバーを露出させてやると益々雰囲気がアップします。

濃淡を付けるとき、外部と接触する機会の多い凸部分は薄く、反対にトリガーガードの根元や内側、セレーションの溝部分などの凹部は濃くイメージしています。
エアブラシで噴霧量を絞って塗装しています。



今回は上塗りにG.Smith.Sの「銃 I」を使いました。
以前「オラガバニスト」のあじゃさんが九四式自動拳銃で使われていた塗料で、その仕上がりが素晴らしかったので自分も今回選んでみました。
G.Smith.Sの塗料は量のわりに高価なので、使うのは今回が全くの初めてです。
「銃 I」はご覧のように、WAの亜鉛黒染めとほとんど同じ色をしていました。
これも下地のシルバーが利いてるせいかもしれませんが、インナーシャーシを組み込んでも違和感無くきまりそうですね♪
今回はフレーム・スライドの塗装のその後。

一度全体をシルバーに塗装した後、黒系の塗料で薄く上塗りしました。
下にシルバーがあるせいで、上塗りに濃淡をつけたとき薄いところではシルバーが透けて見えます。
その雰囲気が普通に塗装した場合より、俄然金属感が現れるので気に入ってます。
今回はまだ吹きっぱなしの状態ですが、ここから更にスポンジヤスリなどでエッジを擦ってシルバーを露出させてやると益々雰囲気がアップします。

濃淡を付けるとき、外部と接触する機会の多い凸部分は薄く、反対にトリガーガードの根元や内側、セレーションの溝部分などの凹部は濃くイメージしています。
エアブラシで噴霧量を絞って塗装しています。



今回は上塗りにG.Smith.Sの「銃 I」を使いました。
以前「オラガバニスト」のあじゃさんが九四式自動拳銃で使われていた塗料で、その仕上がりが素晴らしかったので自分も今回選んでみました。
G.Smith.Sの塗料は量のわりに高価なので、使うのは今回が全くの初めてです。
「銃 I」はご覧のように、WAの亜鉛黒染めとほとんど同じ色をしていました。
これも下地のシルバーが利いてるせいかもしれませんが、インナーシャーシを組み込んでも違和感無くきまりそうですね♪
2011年04月22日
メタルグリップの塗装剥離
中古格安で買ったベレッタM1934の仕上げ直し進行中です。
今回はグリップに手を付けました。

前のオーナーがどういう使用をしていたのか想像が膨らみますが、価格が ¥5600-という格安の一因にもなってそうな傷だらけのグリップ。
新品のピカピカ状態と比べると非常に味のあるリアルダメージ姿なんですが、黒塗装が削れた下からは亜鉛ダイキャストの地が覗いています。
実銃はたしか樹脂製のグリップなんで、いくら味が出ててもやはりそこは違うってことで仕上げ直しです。

まずはメダリオンを外します。
ピンポンチで裏側の穴から押しだすと、結構厚みのあるスポンジ両面粘着シートで貼付けてありました。
後は塗装を剥離するんですが、結構硬そうな塗装でうまく剥離出来るか心配です。

いつもの様にクッキー缶のフタの裏で、カンペのペイントリムーバーを塗りました。
最初のうちは変化が現れませんでしたが、数分後にはブスブスと塗膜が浮き上がってきました。

見事剥離成功!
カンペ大先生、連戦連勝です♪
さて、このグリップをどう仕上げ直そうか色々とイメージが湧いてきます。
あと、スポンジ粘着シートを手に入れないとですね。
ただの両面テープだと厚みが無くなって、そのままだとメダリオンが奥に沈んでしまいます。
今回はグリップに手を付けました。
前のオーナーがどういう使用をしていたのか想像が膨らみますが、価格が ¥5600-という格安の一因にもなってそうな傷だらけのグリップ。
新品のピカピカ状態と比べると非常に味のあるリアルダメージ姿なんですが、黒塗装が削れた下からは亜鉛ダイキャストの地が覗いています。
実銃はたしか樹脂製のグリップなんで、いくら味が出ててもやはりそこは違うってことで仕上げ直しです。
まずはメダリオンを外します。
ピンポンチで裏側の穴から押しだすと、結構厚みのあるスポンジ両面粘着シートで貼付けてありました。
後は塗装を剥離するんですが、結構硬そうな塗装でうまく剥離出来るか心配です。
いつもの様にクッキー缶のフタの裏で、カンペのペイントリムーバーを塗りました。
最初のうちは変化が現れませんでしたが、数分後にはブスブスと塗膜が浮き上がってきました。
見事剥離成功!
カンペ大先生、連戦連勝です♪
さて、このグリップをどう仕上げ直そうか色々とイメージが湧いてきます。
あと、スポンジ粘着シートを手に入れないとですね。
ただの両面テープだと厚みが無くなって、そのままだとメダリオンが奥に沈んでしまいます。
2011年04月16日
下地シルバー
中古ベレッタM1934ミルスペックを ¥5,600-で購入、そして現在仕上げ直し中であります。

下地はステンレスシルバーで、そのままでも完成にしていいぐらいまで仕上げます。
ステンレスシルバーは一週間の乾燥で表面硬度3H、一ヶ月で6H、最終的にはメッキ並みの被膜になるとか。
あとは黒系の塗料を更に重ねて、出来たらエイジング処理までやる予定です。
あるいは使用によって自然に剥げるにまかせるか・・・。
使う事で味が出てくる塗装なんていいですよねw

例の刻印は奇麗に無くなってます。
ヒケも無いよw
でも中古ならではの小傷は埋めずに残してたりします。
これも味です♪

話は変わりますが、ガンケースというか、ライフルケースを買ってみました。
自分は外に持ち出す事はしないので、今までこういうのは持ってなかったんですが、先月の地震でコレクションに被害が出たりしたので、出しっ放しのディスプレイを改める事に。
しかしこのケース、ただものじゃありません。

デカイんですw
M4がマガジンつけたまま余裕で2丁入りますw
なんかこの上で寝られそうな感じのデカさです。

試しにガバを置いてみました。
デカ〜〜w
ガバなら十数丁は余裕で収まりますね。
自分のコレクション全部入ります。
一個一個箱から出し入れするのが面倒なので、これに全部並べて収納しておくのも良いかな。
プラノ製ダブルスコープドライフル/ショットガンケース
Made in USA
下地はステンレスシルバーで、そのままでも完成にしていいぐらいまで仕上げます。
ステンレスシルバーは一週間の乾燥で表面硬度3H、一ヶ月で6H、最終的にはメッキ並みの被膜になるとか。
あとは黒系の塗料を更に重ねて、出来たらエイジング処理までやる予定です。
あるいは使用によって自然に剥げるにまかせるか・・・。
使う事で味が出てくる塗装なんていいですよねw
例の刻印は奇麗に無くなってます。
ヒケも無いよw
でも中古ならではの小傷は埋めずに残してたりします。
これも味です♪
話は変わりますが、ガンケースというか、ライフルケースを買ってみました。
自分は外に持ち出す事はしないので、今までこういうのは持ってなかったんですが、先月の地震でコレクションに被害が出たりしたので、出しっ放しのディスプレイを改める事に。
しかしこのケース、ただものじゃありません。
デカイんですw
M4がマガジンつけたまま余裕で2丁入りますw
なんかこの上で寝られそうな感じのデカさです。
試しにガバを置いてみました。
デカ〜〜w
ガバなら十数丁は余裕で収まりますね。
自分のコレクション全部入ります。
一個一個箱から出し入れするのが面倒なので、これに全部並べて収納しておくのも良いかな。
プラノ製ダブルスコープドライフル/ショットガンケース
Made in USA
2011年04月08日
持ち手について
皆さん、ハンドガンなどの塗装の時はどんな持ち手を付けますか?
自分は以前は割り箸を使っていましたが、小さなパーツなら良いですがスライドやフレームとなると不安定になってしまって困っていました。
で、この頃はもっと便利でお手軽な方法を編み出したので、今回はその紹介をしてみます。
本当にお手軽なんですが、写真のように雑誌を数十ページほど引き抜いて丸めます。
けっこう硬く、きつめに巻いてガムテープで留めるのがコツ。
丸めた端をこのように潰しても、けっこう抵抗があるくらいが良いです。
そして潰しながら・・・。
スライドに突っ込んだり、
フレームに突っ込んだり。
丸めた雑誌が反発して中で広がろうとするので、簡単には抜けません。
割り箸の時はガムテープや両面テープで貼付けたりしてたので、面倒くさかったし、剥がれ落ちるのも心配だったりしましたが、この方法は本当にラクチンですよ!
塗り残しを作りたくない場合も、簡単に位置をずらせます。
どうだ!!
このまま逆さまにしても落ちません。
(振ったりするとダメですよw)
というわけで、中古で買ったベレッタM1934の偽鉄塗装に着手する準備が整ったのでした。