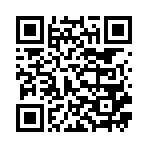2022年03月30日
ブルーイング始めるかぁの15
ペガサスシリンダーのブルーイングに進む。
まずはブルーイング前研磨作業だが・・・

ざっくりとリューターのワイヤーブラシで全体の黒皮膜を取り除こうと思ったのだが、シリンダーの亜鉛が他のパーツと比べてなんか柔い感じで、ブラシでやんわり触れてるだけでも亜鉛が抉れてくるので、ヤバいと思って途中で切り上げる。
ワイヤーが届かなかったシリンダーストップノッチの中を磨く方法を考えたが、マイナスの精密ドライバーの先端にサンドペーパーを両面テープで貼り付け、それでシコシコ地道にやるという方法が楽そうだ。

ノッチを磨いたら、何より先にそこだけブルーイングを済ませておく。
全体の仕上がりを考えるとその方が綺麗にいくだろう。

ノッチのブルーイングが済んだら、次はフルートの研磨。
メッキモデルだとこのフルートの中がガサガサだったりするのがあるんだけど、あれは汚くて嫌だね。
などと呟きながらピカピカに磨く。

フルートを磨き終えたら、シリンダーの外周面と前面を磨く。
写真は400番で磨いたところ。
先にブルーイングを済ませたノッチ部分が綺麗に残って、フルートの外縁もエッジが綺麗に出ている。
まずはブルーイング前研磨作業だが・・・

ざっくりとリューターのワイヤーブラシで全体の黒皮膜を取り除こうと思ったのだが、シリンダーの亜鉛が他のパーツと比べてなんか柔い感じで、ブラシでやんわり触れてるだけでも亜鉛が抉れてくるので、ヤバいと思って途中で切り上げる。
ワイヤーが届かなかったシリンダーストップノッチの中を磨く方法を考えたが、マイナスの精密ドライバーの先端にサンドペーパーを両面テープで貼り付け、それでシコシコ地道にやるという方法が楽そうだ。

ノッチを磨いたら、何より先にそこだけブルーイングを済ませておく。
全体の仕上がりを考えるとその方が綺麗にいくだろう。

ノッチのブルーイングが済んだら、次はフルートの研磨。
メッキモデルだとこのフルートの中がガサガサだったりするのがあるんだけど、あれは汚くて嫌だね。
などと呟きながらピカピカに磨く。

フルートを磨き終えたら、シリンダーの外周面と前面を磨く。
写真は400番で磨いたところ。
先にブルーイングを済ませたノッチ部分が綺麗に残って、フルートの外縁もエッジが綺麗に出ている。
2022年03月24日
ブルーイング始めるかぁの14
タナカM19ペガサスVer.3のブルーイング
前回のサイドプレートに続き、金属パーツ「ヨーク」を。

まずは最初の黒皮膜を除去し、表側をサイドプレート同様400番のペーパーから3000番のシャイネックスまで磨きあげる。
R面を基調とする複雑な形状だが、それほど難しくはなかった。
ここまで綺麗に磨き上げると、我ながら惚れ惚れとする。

裏側はほとんど手をつけず、最初にリューターのワイヤーブラシで皮膜を剥いだところまでにとどめる。
組んだ時にフレームとの間に隙間が開いては困る。


ブルー液はやはり希釈したアルミブラックでは赤茶色になったので、そこからEX.BLUEにチェンジ。
すると赤茶色が剥けて、このようなブルーに変化した。
いまだによく解らないブルー液の不思議。
前回のサイドプレートに続き、金属パーツ「ヨーク」を。

まずは最初の黒皮膜を除去し、表側をサイドプレート同様400番のペーパーから3000番のシャイネックスまで磨きあげる。
R面を基調とする複雑な形状だが、それほど難しくはなかった。
ここまで綺麗に磨き上げると、我ながら惚れ惚れとする。

裏側はほとんど手をつけず、最初にリューターのワイヤーブラシで皮膜を剥いだところまでにとどめる。
組んだ時にフレームとの間に隙間が開いては困る。


ブルー液はやはり希釈したアルミブラックでは赤茶色になったので、そこからEX.BLUEにチェンジ。
すると赤茶色が剥けて、このようなブルーに変化した。
いまだによく解らないブルー液の不思議。
2022年03月20日
ブルーイング始めるかぁの13
前回サイドプレートのブルーイングで、最後赤茶色になってしまって大失敗。
今回のやり直しではブルー液を変更する。
前回希釈したアルミブラック、今回はHWパーツと同じEX.BLUE。

ワシャワシャ〜っと3000番シャイネックス表面を磨き。
この曇った表面がブルー液でどう変化するのか。



EX.BLUE液は希釈せず、原液のまま塗布してるので反応が早いが、経過はアルミブラックの時と同じように進む。
ブルー液を染み込ませたボロキレで塗布する方向を横方向に一定にしていると、ブルーイングの表面状態もそれに合わせて横方向に流れるように皮膜を形成する。
最初のワシャワシャはもう消えて無くなる。
前回はこの後どんどん赤茶色に移行して行って、それ以上色の変化がなくなってしまった。
アルミブラックの希釈液は1年以上保管してあったものだから変質していたのだろうか?


EX.BLUEは逆に青く。
むしろ青すぎて、また本体のHWパーツとは差がついてしまった。
あとサイドプレートの広い面を均一に染めるのはかなり難しい。
ここはもう、完璧を追い求めすぎないという最初のテーマ通り、この辺で妥協することにしよう。
しばらく放置すると黒っぽく変わるかもしれないという願いをかけて、次のパーツへ進む。
今回のやり直しではブルー液を変更する。
前回希釈したアルミブラック、今回はHWパーツと同じEX.BLUE。

ワシャワシャ〜っと3000番シャイネックス表面を磨き。
この曇った表面がブルー液でどう変化するのか。



EX.BLUE液は希釈せず、原液のまま塗布してるので反応が早いが、経過はアルミブラックの時と同じように進む。
ブルー液を染み込ませたボロキレで塗布する方向を横方向に一定にしていると、ブルーイングの表面状態もそれに合わせて横方向に流れるように皮膜を形成する。
最初のワシャワシャはもう消えて無くなる。
前回はこの後どんどん赤茶色に移行して行って、それ以上色の変化がなくなってしまった。
アルミブラックの希釈液は1年以上保管してあったものだから変質していたのだろうか?


EX.BLUEは逆に青く。
むしろ青すぎて、また本体のHWパーツとは差がついてしまった。
あとサイドプレートの広い面を均一に染めるのはかなり難しい。
ここはもう、完璧を追い求めすぎないという最初のテーマ通り、この辺で妥協することにしよう。
しばらく放置すると黒っぽく変わるかもしれないという願いをかけて、次のパーツへ進む。
2022年03月15日
ブルーイング始めるかぁの12
<大失敗>
HWパーツの染めが前回で終了したので、いよいよ金属パーツを染める。

サイドプレートから手を付ける。
400番のペーパーから3000番のシャイネックスまで番手を上げて、綺麗に磨き上げた。
ま、多少細かい傷が見えるが、普通に触っていれば付くようなレベルだし、ブルーイングの皮膜が生成される過程で見えなくなると予想。

水で薄めたバーチウッドのアルミブラックでやってみる。
ボロ布に染み込ませ、雑巾の硬く絞った程度で、染めるパーツが液でビチョビチョにならないことが肝心。
サーっと拭った後、一瞬遅れてスーッと乾く感じで。
これがいつまでもビチャビチャ液が乗ってる状態だと、染まり方が汚くなるのが解った。
そう、実はそれで失敗して、これはやり直しで2回目である。


うおっ、全体が綺麗に熱帯魚のようなブルー。
だが求めている色では無い。

ブルーだったのが今度は黄色に変わる。
こんなに色が変化してても、まだ全然皮膜ができている雰囲気は無い。


あっ!来たかも〜。
だが部分的に赤茶色で、液を弾く感じにならず、まだまだ染めたりてない感じの部分を追い込む。

そしたら良い感じの黒かった部分も赤茶色に変わり、表面が荒れて来始めた。
全然HWパーツと合わない色になってしまった。
ピカールで撫でたら簡単に縁が剥げた・・・。
大失敗
なんだこれ、超難しいぞ。

ささっと1500番のペーパーで水研ぎして剥がす。
水研ぎは楽チン、あっという間に除去。
ああ、急に上手くいく自信がなくなって来た。
HWパーツの染めが前回で終了したので、いよいよ金属パーツを染める。

サイドプレートから手を付ける。
400番のペーパーから3000番のシャイネックスまで番手を上げて、綺麗に磨き上げた。
ま、多少細かい傷が見えるが、普通に触っていれば付くようなレベルだし、ブルーイングの皮膜が生成される過程で見えなくなると予想。

水で薄めたバーチウッドのアルミブラックでやってみる。
ボロ布に染み込ませ、雑巾の硬く絞った程度で、染めるパーツが液でビチョビチョにならないことが肝心。
サーっと拭った後、一瞬遅れてスーッと乾く感じで。
これがいつまでもビチャビチャ液が乗ってる状態だと、染まり方が汚くなるのが解った。
そう、実はそれで失敗して、これはやり直しで2回目である。


うおっ、全体が綺麗に熱帯魚のようなブルー。
だが求めている色では無い。

ブルーだったのが今度は黄色に変わる。
こんなに色が変化してても、まだ全然皮膜ができている雰囲気は無い。


あっ!来たかも〜。
だが部分的に赤茶色で、液を弾く感じにならず、まだまだ染めたりてない感じの部分を追い込む。

そしたら良い感じの黒かった部分も赤茶色に変わり、表面が荒れて来始めた。
全然HWパーツと合わない色になってしまった。
ピカールで撫でたら簡単に縁が剥げた・・・。
大失敗
なんだこれ、超難しいぞ。

ささっと1500番のペーパーで水研ぎして剥がす。
水研ぎは楽チン、あっという間に除去。
ああ、急に上手くいく自信がなくなって来た。
2022年03月11日
ブルーイング始めるかぁの11
ブルーイングの済んだHWパーツを合わせてみた。



なかなか良い感じに出来てるのではないか。
箱だしのHWと比べると断然良い。
あまり仕上がりの目標値を上げ過ぎない事が大事だ。
ハードルを高くし過ぎると気軽にトライ出来なくなる。
自分が初めてブルーイングにトライした素材はマルシンのコマンダーのキットだった。
値段は10K切ってたと思う。
失敗しても精神的ダメージが少なくて済む。
そこそこ上手くいったと思っているが。



フレーム側よりバレルの方が上手くいった。
次はサイドプレート、ヨーク、サムピース、シリンダーとメタルパーツのブルーイングに進む。
HWパーツと上手く色合わせできれば良いのだが、頑張ってやってみよう。



なかなか良い感じに出来てるのではないか。
箱だしのHWと比べると断然良い。
あまり仕上がりの目標値を上げ過ぎない事が大事だ。
ハードルを高くし過ぎると気軽にトライ出来なくなる。
自分が初めてブルーイングにトライした素材はマルシンのコマンダーのキットだった。
値段は10K切ってたと思う。
失敗しても精神的ダメージが少なくて済む。
そこそこ上手くいったと思っているが。



フレーム側よりバレルの方が上手くいった。
次はサイドプレート、ヨーク、サムピース、シリンダーとメタルパーツのブルーイングに進む。
HWパーツと上手く色合わせできれば良いのだが、頑張ってやってみよう。
2022年03月08日
ブルーイング始めるかぁの10
ブルーイング前の下準備として、2000番のペーパーで磨いた後脱脂洗浄、それからモデラで表面潰し、3000番のシャイネックスで最終磨き。
前回はこのあと銀みがきクロスで艶出しまでやったが今回はやめた。
磨いた後ツヤは出たけど折角の金属光沢がくすんでしまったから。
毎回手探りなのは、これだ!という結果をいまだに達成できていないから。


ヒケを綺麗に処理して、下準備としてはまずまず。


ブルーイングの初期段階の状態。
平面部よりR面の方が綺麗にムラなく染まる。
↓最終的に

表面が荒れてくる前にブルーイングを切り上げる「見切り」が毎回むずかしい。
わざとらしいほどの青ピカ銀色になっても、最後に銀磨きクロスで拭き上げると黒くなる。
金属光沢を消してしまうのは素材が金属ではなく樹脂のためか?(でもツヤは出る)
銀みがきクロスとは厚めで柔らかな不織布に研磨剤が練り込まれたもので、他にも銅みがきクロスや金みがきクロスなどバリエーションがある。
研磨剤がどの番手に相当するのかは明記されていない。
あと、みがきクロスで磨いた後、以前ビッグマグナムで購入するともらえてた黄色いクロスで乾拭きするとより一層ツヤ光沢が増すので拭き拭きする。
いつでも気が向いた時はビッグマグナム特製クロスで乾拭きすると艶が出るのでおすすめだ。
前回はこのあと銀みがきクロスで艶出しまでやったが今回はやめた。
磨いた後ツヤは出たけど折角の金属光沢がくすんでしまったから。
毎回手探りなのは、これだ!という結果をいまだに達成できていないから。


ヒケを綺麗に処理して、下準備としてはまずまず。


ブルーイングの初期段階の状態。
平面部よりR面の方が綺麗にムラなく染まる。
↓最終的に

表面が荒れてくる前にブルーイングを切り上げる「見切り」が毎回むずかしい。
わざとらしいほどの青ピカ銀色になっても、最後に銀磨きクロスで拭き上げると黒くなる。
金属光沢を消してしまうのは素材が金属ではなく樹脂のためか?(でもツヤは出る)
銀みがきクロスとは厚めで柔らかな不織布に研磨剤が練り込まれたもので、他にも銅みがきクロスや金みがきクロスなどバリエーションがある。
研磨剤がどの番手に相当するのかは明記されていない。
あと、みがきクロスで磨いた後、以前ビッグマグナムで購入するともらえてた黄色いクロスで乾拭きするとより一層ツヤ光沢が増すので拭き拭きする。
いつでも気が向いた時はビッグマグナム特製クロスで乾拭きすると艶が出るのでおすすめだ。
2022年03月06日
ブルーイング始めるかぁの9
フレームのブルーイングが終わったあとはバレルの番。
4インチのバレルだが、HW樹脂だけあって見た目のサイズにもかかわらずズシリと重い。


リブの厚みもかなりあるので重量がそこそこ稼げるのだが、表面を削るとそれなりにヒケがあるのがわかる。
銃口から1cmほど後ろにグルリとくびれのようにヒケがある。
バレルのR面を維持しつつ、ヒケを消していくのは意外と大変だ。

リブのサイド面を削る。
その際、R面を傷つけないようマスキングするのは必須。


最初の400番で削るのは、表面の皮膜除去とヒケを処理することが目的。
なんとかヒケを処理した段階がこちらだ。
この後はより細かい目のサンドペーパーで表面状態を整えて行き、ツルツルになるまでをめざす。
4インチのバレルだが、HW樹脂だけあって見た目のサイズにもかかわらずズシリと重い。


リブの厚みもかなりあるので重量がそこそこ稼げるのだが、表面を削るとそれなりにヒケがあるのがわかる。
銃口から1cmほど後ろにグルリとくびれのようにヒケがある。
バレルのR面を維持しつつ、ヒケを消していくのは意外と大変だ。

リブのサイド面を削る。
その際、R面を傷つけないようマスキングするのは必須。


最初の400番で削るのは、表面の皮膜除去とヒケを処理することが目的。
なんとかヒケを処理した段階がこちらだ。
この後はより細かい目のサンドペーパーで表面状態を整えて行き、ツルツルになるまでをめざす。